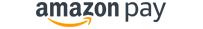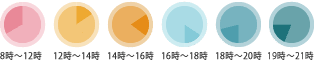- おすすめキーワード
-

【連載】 原田和典のJAZZ徒然草 第92回
- JAZZ
- JAZZ徒然草
2014.08.29
オーネット・コールマンの音楽をオールスター・メンバーが祝い、ティム・バーンのユニット“Decay”ではライアン・フェレイラが天才的なギター・プレイを披露。いつだってブルックリンはエキサイティングな街だぜ
 |  |
 |  |
今回のニューヨーク行きで最も楽しみにしていたプログラムのひとつが、6月12日にブルックリンのプロスペクト・パーク内で開かれた無料コンサート「Celebrate Ornette: The Music Of Ornette Coleman Featuring Denardo Coleman Vibe」(「ブルーノート・ジャズ・フェスティヴァル」の一環として開催された) だ。
ようするにオーネット・コールマンの音楽をみんなでお祝いしようというプログラムだが、出演者欄にご本尊の名が記載されることは最後までなかった。が、会場を埋め尽くした観衆は「最後まで期待は捨てずにおこう。もし演奏できる体調ではないとしても、顔ぐらいは出すのではないだろうか」と思いながらブルックリンへの道を向かったはずだ。ちなみに事前に告知されていた参加者は以下の通り。
●デナード・コールマンと彼のバンド(アル・マクダウェル、トニー・ファランガ、チャールズ・エラービー、アントワン・ロニー)
●ゲスト:マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカ、ビル・ラズウェル、ブルース・ホーンズビー、フリー(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)、デヴィッド・マレイ、ジェリ・アレン、ヘンリー・スレッギル、ジェームズ・ブラッド・ウルマー、ジョン・ゾーン、ローリー・アンダーソン、ネルズ・クライン、パティ・スミス、ラヴィ・コルトレーン、セヴィアン・グローヴァー、サーストン・ムーア、アフリカ・バンバータら多数。
バンバータは出なかったが、ほかにブランフォード・マルサリス、ジョー・ロヴァーノ、ウォレス・ロニー・ジュニア(ウォレス・ロニーとジェリ・アレンの間に生まれた。父と同じくトランペットを吹くが、賢くもマイルス・デイヴィスを追ってはいない) もプレイした。そしてオープニングではなんと、一切告知されていなかったソニー・ロリンズが登場し、コメントを述べた。
メモをとるのも忘れるほどびっくりしたので記憶に頼るが、とにかく「共に長生きしてきた掛け替えのない同志であり、常にポジティヴな言葉で自分を勇気づけてくれた」というようなことを語っていたと思う。そしてオーネットも予想通り登場し、「対立や争いは無益。互いに助け合うことが重要だ」などと述べていたような気がする。
ここでロリンズ、オーネットは一度下がり(ロリンズの出番はこれで終わり)、デナードたちの演奏が始まる。いきなりゲストにフリーが出たので、ステージにはマクダウェル、ファランガ、フリーと3人のベース奏者が並んだ形となる。フリーはジャコ・パストリアスの影響モロ出し、マクダウェルはギター的な音色でソリストに絡む。重厚なプレイで際立っていたのはアップライト・ベース担当のファランガだ。彼は本当に音程がいい。管楽器陣ではロヴァーノが王者の貫禄で音色、フレーズ、リズム共に快感を与えてくれた。スレッギルの表情はいささか苦しそうだったが、プレイそのものはさすがというしかない。マレイはどの曲でもソロ・パートの最後でハイノートを絶叫するという、ここ25年ぐらいずっとやっているやかましいスタイルを飽きずに繰り返し個人的には感興ゼロ。インディア・ナヴィゲイションやブラック・セイントに吹き込んでいた頃のプレイを聴き返して、もっと丁寧にひとつひとつの楽曲に向き合うよう態度を改めてはどうか。
「ブロードウェイ・ブルース」、「ターンアラウンド」、「ランブリン」などが演奏された後、白く塗装されたアルト・サックス(プラスチック製ではない)片手にオーネットが合流する。正直言ってあまり多くを語りたくないが、今のコンディション(なにしろもう84歳、おととしには大病もしているのだ)で可能なことはしっかり出し切ったのではないだろうか。いきなり「ターンアラウンド」のメロディを吹き始めたのにも驚かされたけれど、御大はおそらく、その十数分前にこの曲が同じ場所で演奏されていたことを認知していなかったに違いない。オーネットの出演時間は、それでも20分はあったと思う。その後パティ・スミスがレニー・ケイのギターをバックに詩を朗読し、クラリネットを吹いた。
オーネット・コールマンとパティ・スミス
休憩後、プロデューサーのハル・ウィルナーが思い出話を披露。70年代後半、オーネットをテレビ番組「サタデイ・ナイト・ライヴ」に引き合わせたのもウィルナーだったそうだ。その後はローリー・アンダーソン(ヴァイオリンも弾いた)とジョン・ゾーンとビル・ラズウェル、サーストン・ムーアとネルズ・クラインなどの興味深い即興セット(個人的には単なるオーネット曲のカヴァーよりも、はるかに楽しめた)が続いたが、ブランフォード・マルサリスとブルース・ホーンズビーのデュオはふたりの手先の器用さを示しただけだったように思える。ラストに再びデナード率いるジャズ・バンドが伴奏に回り、ラヴィ・コルトレーン、ジェームズ・ブラッド・ウルマー、ブランフォード、ロヴァーノ、ラズウェル、マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカらが入れ替わり立ち代り演奏。ジャジューカの笛の後ろで妖しくうごめくラズウェルのベース、椅子にドカッと座って親指奏法で弾きまくるウルマーの存在感にしびれた。ブランフォードとラヴィは線が細くミス・キャストだったと思うが、実は今回のライヴには、“血脈”という裏テーマがある。
マスター・ミュージシャンズ・オブ・ジャジューカ
オーネットの息子で当イベントのプロデューサーも務めたデナードとしては、ジョン・コルトレーンの息子であるラヴィ、エリス・マルサリスの息子であるブランフォード、そしてウォレス・ロニーの息子であるウォレス・ロニー・ジュニアをぜひ同じステージにあげたかったのだろう。が、僕の頭に浮かんだのは、ロック・バンド“亜無亜危異”の歌に登場する「ただその家に生まれただけで」というフレーズだ。
息子といえば、トランペット奏者アダム・オファリルのプレイを「Bar Next Door」(129 Macdougal St, Manhattan)で聴くことができた。「音楽院などの教育機関で学んでいる成績優秀な“未来の大器”に演奏の場を与える企画」(店内の張り紙より)の一環だ。「なぜ教育機関限定?」という気持ちも起こらないわけではないが、いまやジャズはコンサーヴァトリーやユニヴァーシティやカレッジで学ぶもの。「ストリート音楽としてのジャズ」を満喫するには、我々が生まれるのは60年ほど遅すぎた。アダムはチコ・オファリルの孫、アルトゥーロ・オファリルの息子。すさまじいサラブレッドだ。バンドスタンドにはベース奏者、ドラマーがスタンバイしており、つまりこれはトランペット・トリオによる演奏であることを意味する。ラテンの血バリバリのすさまじいトランペット・トリオが聴けると大いに期待し、1曲目がエリック・ドルフィーの「ミス・アン」であったことにも喜びが倍増したが、テーマ・メロディを6小節ほど過ぎたころから“何かおかしいぞ”と思った。まず旋律が吹けていない。アドリブもアドリブというよりも原メロディのいかさない変奏で、同じところをグルグル回っているようで全然先にいかない。せっかく輝かしい音色を持っているのに、どうしたものだろう。
アダム・オファリル
いっぽう、ブルックリンのアーバン・メドウ近郊で行なわれた「Red Hook Jazz Festival」では、ベテランのアルト・サックス奏者ティム・バーン率いる“Decay”が圧巻だった。まさしくフェスのトリにふさわしい快演、スリルと興奮に満ちたサウンドは、それまでの出演バンドが作り出してきただらけた空気を一蹴した。
野外フェス、しかも家族連れも多いということで(大人10ドル、子供無料)、ティムは妙にユーモラスなMCを披露し、1曲あたりの演奏も比較的短めだ。だがむせかえるような高濃度サウンドはティム・バーンそのもの、しかもライアン・フェレイラのギターが抜群にいい。ティムのサックスに挑みかかるようなカッティング、コード、時空を歪ませるようなソロ。エフェクターを踏み込む下半身は、まるでダンサーのようだ。少年の頃はスキッド・ロウ、ポイズン、モトリー・クルー、ニルヴァーナらに熱中し、その後アラン・ホールズワースをきっかけにジャズに興味を持ってウェス・モンゴメリーやパット・メセニー、デヴィッド・トーン等を聴くようになったという。
それにしてもティムは、本当にいいミュージシャンを見つけ、才能を伸ばす。クレイグ・テイボーン、クリス・スピード、マルク・デュクレ(マーク・デュクレイ)、オスカー・ノリエガ、マット・ミッチェル、チェス・スミス、そしてフェレイラ。かつてはアート・ブレイキーやマイルス・デイヴィスが数々の若手ミュージシャンをシーンに紹介したが、彼らが没して25年にもなる今、その一翼を担っているひとりは間違いなくティム・バーンだ。

ティム・バーン

ライアン・フェレイラ
■原田和典著作関連商品■




最新ニュース
-
2024.04.09
- JAZZ
-
2023.11.21
- JAZZ
-
2023.07.20
- JAZZ
-
2023.04.25
- JAZZ
-
2022.11.24
- JAZZ
-
2022.06.14
- JAZZ
-
2022.05.11
- JAZZ
-
2022.01.19
- JAZZ
-
2021.11.25
- JAZZ
-
2021.08.31
- JAZZ