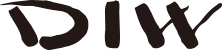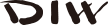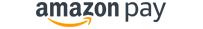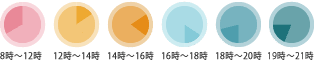アルバム『死ぬ迄踊れ』を8/8にリリースしたFOXPILL CULTのロングインタビューを掲載!
- DIW PRODUCTS GROUP
- ニュース
2018.08.08
diskunion発行の月刊フリーペーパー、FOLLOW-UPの2018.Vol180(7/25発行号)に掲載されたFOXPILL CULTのインタビューの完全版をWEB限定でお届けします!インタビューは†13th Moon†のヤマダナオヒロ氏!誌面ではスペースの都合上割愛となった話題も余すことなく掲載しております!是非アルバムを聴きながらお楽しみください!!
国内インディペンデント・シーンにおいて、作品を出すごとに唯一無二の色濃い存在感を増してきているポスト・ニュー・ウェーブ・バンド、FOXPILL CULT(以下:FPC)。彼らが、女性ベーシスト、ハラワタ夢々の加入後初となる4作目のフルアルバム『死ぬ迄踊れ』を、DISK UNION内のレーベルROMANATIONから8月8日にリリースする。ほぼ全曲の作詞作曲を手がけ、別口で劇団の音楽監督も務める中心人物の西邑卓哲(Vo/G etc)と、キープレイヤーであるShinpei Mörishige(G/Synth/)の2人に、彼らの曲にもたくさん出てくる<時計>だらけの喫茶店にて話を聞いた。
インタビュー : ヤマダナオヒロ(nAo12xu / †13th Moon†)
■ 間にミニアルバムとかも出してるので、傍から見てると常にいろいろ出し切ってそうな感じがすごいあるんだけど、そんな中でついに4作目となるフルアルバムを出すわけです。ずばりどんな出来ですか?
西邑(以下:西): わりとファーストアルバムみたいな勢いですね。バンドっていつ解散するかわからないじゃないですか。去年ワンマンやって「ここでキメよう!」と思った時に腰を壊して入院して、その時にバンドについていろいろ考えたんですよ。「バンドってこうじゃなきゃいけない」とか「「バンドを続けること自体が目的になってしまってるんじゃないか」とか。でも突き詰めたら「もっと自由でいいだろ」って、なんなら「いつ解散したっていいじゃん」てなって。だったら、現在のメンバーの個性や演奏の色が強く出せたらなと。結果的に一番バンドっぽい作品になったと思います。
Mörishige(以下:M): 普通アルバムで4枚目と言ったらマニアックになりがちだけど、一番わかりやすくなったよね。
■ まず1曲目「死ぬ迄踊れ」から続く「出でる時報男」を聴いて感じたのが、骨格と皮膚としてFPCという母体がありつつも、血や肉として音色やリズム、楽曲、歌メロなどに滲み出てくる<ポジパン>とか<デスロック(Gothic Punk)>のアルバムの感触や、ニューウェーブの中でもダークな要素をもったポストパンクの雰囲気がわかりやすく出ているなと。
◆FOXPILL CULT - 出でる時報男 (4th Album「死ぬ迄踊れ」より)
西: 一時期、特に俺とMörishigeが色々と模索しながら曲をいっぱい書いてるうちに、最終的に「気にせず何でもやろうぜ!」ってなって、自由にやったら出てきたものがコレでした。ポジパンは自分のキャリアの中でも大きく要素があって「ポジパンとはコレだ」っていう固定観念も持ってるんですが、逆に固定観念が強いからこそやれなかった部分もあったんです。FPCの歴史って割と「固定観念とその破壊」のせめぎ合いで、あえて遠くまで飛んでみようとか、色々トライした中で学んできたバランス感覚が、最近ちょっと見えてきた気がします。
■ たくさん作品を残してきたが故に昇華させられるようになった部分?
西: 作品の枚数を出してることと、あとは個人的に演劇の経験も大きいと思いますね。作品を出すと「もっとこうしておけば良かった」という後悔もあるけど、その蓄積から固定観念が崩れてくるというか。意外と自分てこういう人間なんだなってのが良くも悪くもバレて、その先に今の音像があったというか。ギタリストとして俺が得意だったり好きなのって何だろう、とかも含めて素でやった結果です。
■ 最近は自分達で「ポストニューウェーブ」って謳ってるじゃないですか。その言葉は『死ぬ迄踊れ』を聴いて、より凄いしっくり来たんです。ニューウェーブ的な音色を踏まえたうえで、確実にFPCの要素が広がっている。むしろFPCの技の一つとしてニューウェーブがある、みたいな感じで。
M: このアルバムを出す前に会場限定のEPを2枚出したんだけど、それがすごく良い経験でしたね。消去法的に自分達のやりたいことがシェイプされて、サウンドも洗練されていったと思う。そして自分達の行きたい道、行くべき道が自ずと浮かび上がってきましたね。
◆FOXPILL CULT - CULTIZM (会場限定シングル「NOU!」より)
■ ツイッターでは今作は「難産でした」って書いてましたよね?
西: 結構色んな意味で時間は割とかかったんですよ。兎に角このアルバムは、<現在のメンバーでの演奏>を重視していたので出来る限り修正しないでやりました。この一年間は、メンバーそれぞれの得意なことを想定しながら曲を作ってたんです。ベースもデモの段階から指で弾いたり、このギターフレーズは多分Mörishigeが得意だな、とか。僕はレコーディング・エンジニアもやるので「価値のある録音って何だろう?」みたいな、その時代にその作品をわざわざ出した価値が生まれるか否かっていう部分も考えるんです。そのためには、各メンバーのプレイの熱が篭ってってて、それぞれがリンクして、それがちゃんと(音として)録れてないといけない。じゃないと、メンバーが変わっても別に関係ないじゃん、ってなる。でも、バンドってやっぱりその人にしかない<ニュアンス>がすげぇあって。上手い下手ではなく、その<ニュアンス>が録れるまではやるっていう拘りはありましたね。
M: 今回は結構、何十テイク、何百テイク、と千本ノックみたいな感じでものすごい数を録ったと思います。西邑君にはFPC以外に舞台音楽とかPhaidiaやMadame Edwardaというポジパン・バンドでの経験があるように、僕には最近だとBlieANとかTHE DIDITITS、†13th Moon†など色んなバンドでギターや鍵盤、ベースを弾いてきた経験があって。それを通じて、自然とやれる事もやりたい事も増えて散らかってきていたんです。今作では、そんな僕のアプローチのレンジが広くなったところを、西邑君が上手くピックアップしてくれて。だから僕も1人のプレイヤーとしてシェイプされた自分を作品の中に余すことなくぶつけられたかな。西邑君がどこまで意識的に僕のそういう部分を引き出したのかは窺い知れないけれど、結果的に自然な形でディレクションされていったと思います。
■ 2人がポジパン、ニュー・ウェーブのルーツを持つのはよくわかるんだけど、西邑君がよくルーツとして、ヒップホップのCypress Hill『Black Sunday』を挙げてるでしょ?具体的にどういう風に影響を与えてるのか直接聞いてみたいなって思ってて。
西: CYPRESS HILL『Black Sunday』は本当に影響がデカくて。かつてDARKSIDE MIRRORSというバンドでギターを弾いていた時に「君はこれが良いね」って言われた部分はほぼCYPRESS HILL的な音色から来てて。その後MADAME EDWARDAにギタリストとして加入した時も「CYPRESS HILLで出てきたちょっと不穏な半音階みたいなのがポジパンに似合うんだな」と感じることが多くて、その解釈から始まってるんですよ。あとは、これ多分理解し辛いと思うんだけど、FPCの曲の書き方って、実はすごくヒップホップに近いんです。僕らはラップもしないし、ブラックミュージック要素も少なめですけど、例えば大ネタとして、<ポジパン>と<サンバ>を混ぜる、みたいに、要素と要素を掛け合わせる作り方を結構するんです。そしてそれぞれの要素の接着剤は<歌メロ>なんですよ。歌がわかりやすくてポップだったらポップになるし。バックの要素が何であっても日本語で歌ったら日本のポップスかなって皆思う。で、どっちかっていうと僕そっちに命をかけてて。演奏部分にジェームス・ブラウンのサンプリングをもってきて、サビを坂本九の「Sukiyaki」にしちゃおうみたいな。僕らはサンプリングではなく、ロックとして、それらの要素を自分で演奏して組み立ててやってるという。
■ 大ネタがバックにありつつ、歌が全てを繋いでポップに聴こえる仕組みって、悪い意味ではなくアニメやアイドル楽曲の手法と近い感じもしますね。あとそういえばFPCのライブを観ると、オンステージだと、音源で聴くよりもさらに<男の波動>みたいなのが出てますよね?特にプエル君がいた時なんかも祭りを飛び越して、なんか、見世物小屋の獣が放つ波動感まで出てて(笑)。あれは何なんだろう?
西: それもやっぱり自分自身のルーツとしては、パンクよりも先にヒップホップがあるから、FPCにある「ハ!」とか「オイ!」などの掛け声は、実はONYXとかCYPRESS HILLとかちょっと、ウェッサイで掛け合いの入るヒップホップなんですよ。何せ祭りが好きで……的屋の家系なもんで(笑)。
M: 男の波動分かるなあ(笑)。祝祭感がね。
◆FOXPILL CULT - アートサマージ 悪魔の人体時計版(4th Album「死ぬ迄踊れ」より)
■ あと掘り下げたいのが、西邑君の持ってる昭和アングラなテイストや、もっと遡った古代日本のジャパネスク的な奇妙奇天烈感もあると思うんですけど、それはどういう部分から出ているんだろう?
M: ヤマトタケル感がありますよね。日本ならではの神秘性を感じる部分というか。自分には無い要素だけど。
西: 結構日本に対する憧れが元々多分強くて。ちっちゃい頃は結構海外に行っていたんですよ。ずっといたって住んでたっていうよりも割と旅行とかによく行ってる様な家で。年末とかは日本にいない、みたいな。だから逆に京都とかがすごい好きで。多分JAPANとかがエキゾチックなものが好きみたいな。一時期ハマってデビットボウイでもちょっと日本にハマったりとかもする。あの感覚が僕の中で子供の時からずっとあって。で、多分この音源、今までの俺の活動だとちょっと意外がられるかもしれないんですけど。割と思春期って邦楽をまったく聴いてなくて。まあ小学生とかの時とかは聴いてましたけど。ヒップホップでもう一回また日本の音楽に戻ってくるまでは割と聴いてなかったんですよ。だから日本の神秘的部分がすごく憧れの部分としても残ってて。それがどんどん自分の中で増してった結果ここに辿り着いた、という感覚はありますね。
■歌詞についてですが、FPCの歌詞って、一般的な人が聴いたらすごく異物感があるような言葉が並んでいることが多いと思うんですよ。言語も日本語、英語、ドイツ語、フランス語が混ざってくるし、単語でいうと時計、蠅、模型…例えば「焼けた模型」とかよく歌詞に出てくるじゃない?あれらはどうやって生まれてくるのかな?
西: やっぱり文学や演劇の影響がすごくデカいですね。言葉は割と書いてますが、そもそも大枠として物語が先にあるんです。物語を書いて、曲はそれぞれの場面。『死ぬ迄踊れ』を人生だとすると、この曲では喫茶店で喋ってる場面、とか。例えば<時間>て絶対的だけど主観じゃないですか。知識とかによって感じ方も違うしズレてくる。同じ言葉で話し合っているようで話し合ってないようなことが起きる。そういうのが大まかなテーマとして時計という言葉があって、それでその人体模型の中にオッサンが修理しに入っていく。実際に家にはワンマンとかでも使った人体模型があって。単純に奇妙で面白いなってのもあるし、自分の体内を巡る旅みたいなモチーフがありました。チベットの「死者の書」とか、一回死んでから何か月かで生まれ変わるまでのことが書いてあるんですけど、サイケに近い輪廻観とか、そういうのをぎゅっと詰め込んだ感じなんですよ。
M: その世界観の流れは会場限定のシングルから始まっていたと思うんですよね。西邑君のプロパガンダにかかった訳ではないけど、感覚としてありました。時間や時計、音楽は時間芸術だから始まったら必ず終わるという概念からは逃げられないし。人体模型は、僕ら人間の自分の中に内在する何か逃れられない不変の真理がテーマなのかとは感じ取りました。結果的に演奏のアプローチとしても無縁ではなかったと思います。
◆FOXPILL CULT - 人体模型への散歩者 feat.ナカムラマサ首(会場限定ミニアルバム「バクマクラ」より)
西: あと結構ウチは歌詞カードが大事だったりして。詩だけ見るとちょっとよく分からないんだけど、歌詞カードの色で「こういうことかな?」って印象が変わったりとか。例えば「これは真実です」って言葉をめちゃめちゃ強い色で書くと伝わりやすいけど、薄い色で書くと嘘っぽく聞こえるみたいな。聴こえる感覚だけじゃなくて、文字を読んだ時の印象や色も含めての総合的な印象を重視してます。まぁCDだとどうしても二次元的な感じになってしまいやすいんですけど、どうにかして<体験>にもっていけないかっていう感覚で書いてますね。
■ 聴覚だけでなく視覚的にも、体感的も<体験>にしたいと。
西: あとはCD=物体としての作品の価値を、やっぱりすごく考えていて。デジタルで売るよりも俺は物体として売りたいっていうのがあるんです。ページをめくる匂いも含めて、そこまでやらないと出来ない体験もあるんじゃないかなって。演劇がそうだと思うんで。
M: アルバムもそうだけど、去年のワンマン、これからやる8月のワンマンの見せ方にも大きく関わってきていると思う。さっき西邑君が言ったように、実際、自分を辿る旅だったような気がしますね。西邑君と旅をしたような。それを解りやすい形でアルバムに出せたと思う。自分の音楽の始まりであったクラシック、そこからニューウェーブ、オルタナティブ、最近ではまたポストパンク。自分の中でそういう時の流れがあって、自分の身体に内在する全てを、時計と人体模型をテーマにしたアルバムを媒介にして、Booちゃんやハラワタ夢々を含めたFPCの4人…いや4人だけじゃなく、プエルとか過去にいたメンバー達も含めて、このアルバムはFPCっていうバンドを辿る旅だったような気がします。概念的なことではあるだけど、本当にサウンドに出来たと思ってます。…ってなんかいいこと言ったわぁ、ラストアルバム感が出ちゃったね(笑)
■ ところで、今回のアルバムは14曲でぎっちりで作って出来たのか、それとも数ある中から厳選したのかな。
西: 基本的には、今回は14曲決め打ちでした。アルバムを作る前に、会場限定シングルなどの時点で取捨選択をしてるので。作ってみてこれちょっと違うなとか。もう全然使わなかった時期の、演奏すらしなかった曲もいっぱいありますし。
M: 実験はその時にしちゃって、だからこそ今作は一切捨て曲なしの14曲だね。
■ 抜粋で楽曲に的を絞って聞いていきたいんですが。「蝿を殺すな」は歌い方も含めて聴いた瞬間にSEX GANG CHIILDREN「Sebastian」(ポジパンを代表する名曲)を感じました。
西: これはその通りモロなんですけど、それこそヒップホップの大ネタ・サンプリングでいえばSEX GANG CHILDRENに長渕剛を混ぜる、みたいな感覚ですね。「せい!」って言うと単純に「せい!」って言うのが返ってくる。「殺せ」って言うのはいかに長渕っぽく「せい!」って言うのかは。それは別に長渕像はそんなうまく出来ないんですけど。
■ あとは5曲目「MEIN REICH」は、もはやJAPANとかDEPECHE MODEとか初期NEW ORDERみたいな感じのダンサブルな所謂80‘sニュー・ウェーブみたいなのをすごい感じて。この辺りはMörishige君のルーツ的要素が大きいんですかね?
◆FOXPILL CULT - MEIN REICH (4th Album「死ぬ迄踊れ」より)
M: 作曲したのはケビンちゃん(西邑の呼称)なんですけど、彼の中にもそういう要素がナチュラルに多分にあって。お互いTM NETWORKとかも好きだし。僕はSOFT BALLETも好きで、当然DEPECHE MODEももちろん大好きでそういうアプローチをしようと思って、自然な形で考えた時に僕のアウトプットは鍵盤にしようと思って、この曲は僕がシンセを弾きました。ちょっと異彩を放つ部分も残しつつ。
西: 割と初期のFPCにこういう曲が多かった時期があって。もともと一時期はベースもいなかったというか、寧ろ楽器が出来るメンバーが全然いなかった時に「打ち込みメインにしよう、それならニューロマだ」みたいな。割とそのニュアンスが強かった時期が一瞬あったんですよ。なので元々そういう分子は持っていつつ、今回Mörishige君がシンセを弾いている曲が欲しいなっていうのはあって…。
M: 多分これは『NEW ROMANCER』とか、僕はまだ参加してなかった初期の頃のFPCのエッセンス…過去にそういう作品があったから、そのエッセンスを今ここに昇華出来たのかなっていう感じはしますね。
◆FOXPILL CULT - NEW ROMANCER(1st Album 「NEW ROMANCER」より)
西: ニューウェーブって、それこそDURAN DURANのプロデューサーがナイル・ロジャース(CHICのメンバー)だったり、DEAD OR ALIVEもKC & THE SUNSHINE BANDをカバーしたりとか。ディスコやファンクに対する憧れみたいな部分があるじゃないですか。JAPANとかも、ブラックなんだけどめっちゃ白人ノリなってますやん、みたいな。憧れてるんだけどてやってるけど形になりきってないモノの面白さみたいなのが結構僕好きで、共感する部分もあるんですよ。日本人だから出来ないファンクの部分とか。それを昇華出来るものとしてニュー・ウェーブが一つあって、僕の中で。
■ それはさっき言ってた日本に対するジャパネスク的な思いともやっぱりシンクロしてくるんでしょうね。
M: うまく出来ないが故の葛藤の部分もきっとサウンドになってると思います。日本人であるが故の葛藤というか。
西: あと僕にとってはメイクに関しても同じで。今でこそヴィジュアル系が存在するから評価される土壌もあるんだけど、メイクをもってしてなれない自分や憧れを表すというか。ちょっと異端的な感覚や、反抗的な部分も含めて表現のひとつとして存在していて。それが曲にもリンクしてきますね。
■ そういえば11曲目「ミラーニューロンの終わり」。これもすごい面白いなと思って。すげえ低音で歌って、インダストリアルとかLAIBACHみたいな感じの。あの曲だけ更に異物感がクセになる感じだったので。
西: あれは結構アルバムの接着としての曲っていう意味合いが強い曲で、作品としてまとめるために「この歌詞をどうしてもいれたい」という部分から作ってるのと、歌詞的に割とヒントが一番多い曲で。そしてすごく嘘臭いものを声として出したい、みたいな。その時に、一個の表現方法として様々なジャンルから、例えばLAIBACHでもD.A.F.とかの空気とかでも、敢えてここは生演奏しない。で、後半はむしろ去年のワンマンの時のベースとドラムのセッションをそのまま入れてて。後半が結構ぐちゃぐちゃなんですけど、去年のアドリブを録音しておいたんでそのまま入れて、そこに僕がギター重ねて。
あと喋るパートもあるんですけど、それは、僕が所属している演劇系の昭和精吾事務所に、詩に特化した、寺山修司のアジテーションの役者さんがいて。割とその方の「いかにアジテートするのか」の部分を見て学んだ手法が入ってたるんですよね。
■ なるほどね。そっか。やっぱり色んな活動の幅が吸収の幅になってそれが作品に出てるんですね。
西: やっぱり舞台の影響が大きいと思います。肉体で作る。肉体と言葉。誰が出てきて、このテンポで歩いてくるので、そこにイントロをつけて下さいっていうのを。やっぱり先に台本があがってるんで。割とこれとかそっちに寄ってる曲ですね。
◆『現し世の揺れ』MV (虚飾集団廻天百眼 舞台『殺しの神戯』より) 西邑は楽曲制作/音楽監督他で参加
■ そうやって説明されると、さっき話した男祭り感とか男の波動とか、フィジカル感みたいなところで全て繋がりますね。静と寂で緩急つけたりとか。
西: 恐らく演劇が、その波動に近いところがあるかなと。例えば低音でドコドコドコドコやるのって、演劇だと怨霊を蹴散らす時とか低音で蹴るとか。そういう時ってだいたい下から地獄っぽいのがやってくるとか。天国を表す時はやっぱり高い声系が多かったり。ミックスを雰囲気に合わせて、心理状態も見据えてやると、僕の望むものになったりして、色んな部分がリンクしてくるんですよ。で、Mörishigeが結構ディレイかけて高音のギターソロが得意だから「多分この人は天使とか天国っぽい何かをやらせた方がいいんじゃないかなぁ」みたいな感覚で(笑)曲をあてたりして、そうやって役者が決まってく感覚ですね。
■ なるほど、そうやって配役が決まるんですね。その際、メンバーには配役のロジック実際に説明するんですか?キミは天使っぽいからここ歌って、とか(笑)
西: 全然しないです(笑)。レコーディングの時も、最後のとこは変拍子だから「ここでね、主人公転ぶんですよ。だから一回変拍子になります」みたいなそういう説明だけですね。
■ しないんだ!じゃあMörishige君も、今この会話で初めて知る部分もあるってこと?
M: そうですね(笑)、今初めて聞いたけど、確かに僕も作品の中で、自分が天使であることには全く疑問を持ったことはないですね。確かに言われてみれば「俺は天使だったんだ」って。
一同: 爆笑
西: 多分それは言わなくても勝手にライブの時やってるじゃん。
M: あはは、まあ羽は生えてるからね(笑)
西: 曲から人に合わせて当て掛けしてった方が、その時このメンバーでやった価値が生まれるんじゃないかって。
M: うんうん、演じることなくね。そう、皆キャラクターを引き出して。
西: 結構うちメンバーが変わってきたりとか、そういうのも含めたからこそ、どうしてもリーダーって、やっぱり僕はバンドを存続しなきゃって気持ちがずっとあったから。継続出来るやり方を求めちゃうんですよ。解散しないやり方を求めちゃう。ってことは、自分の声以外は代用可能な作品にどんどんなっていきがち。でもそれをちょっとやめようって思ったのは、寧ろ真逆にやって「彼がいなかったらもう解散してしまうんだ」みたいなアルバムを作ろうっていうのが、今回バンドっぽさとかポップさに繋がってるんじゃないかと思いますね。そういう意味では、一期一会な「一歩間違えたら危うく出なかったような作品」を残せたかなと思います。
-INFO-
最新作「死ぬ迄踊れ」は、原点回帰と共感不可能な人体時計をテーマに、彼らのルーツの一つであるゴスを彷彿とさせるアプローチや扇動的なパンク ロック、サイケデリック、多国籍の童謡、
更に今夏にサウンドトラックが全国発売される話題のアングラ劇団「虚飾集団廻天百眼」や「昭和精吾事務所」で音楽監督をつとめる西邑卓哲の経験を活かした演劇的要素も多く盛り込まれ、
ファンの間で傑作として名高い2ndアルバム「邪宗門」を彷彿とさせる大作に仕上がっている。
8月24日には下北沢SHELTERでのワンマン公演 「Stations of the Cult2 -死ぬ迄踊れ-」が決定しており、去年披露された組曲的なライブが進化して、ふたたび披露されるとのこと。
チケットはバンドが直接販売する会場限定チケットとe+で購入可能。ワンマンを記念して6ヶ月連続自主企画ライブの開催も決定している。
■e+チケット購入ページURL(パソコン/スマートフォン/携帯共通)
http://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002259621P0030001
-
2018年08月08日 / CD / JPN
-
2016年10月19日 / CD / JPN
-
2016年03月09日 / CD / JPN
最新ニュース
-
2024.01.09
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2023.11.01
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2023.02.23
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.12.27
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.04.14
- DIW PRODUCTS GROUP
MOUNT MOUTH & THE SKA-MANS Shuffling : Maskman Ska(7インチ)発売延期のお知らせ
-
2022.03.15
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.03.03
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.02.21
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.02.21
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.02.16
- DIW PRODUCTS GROUP