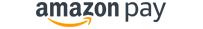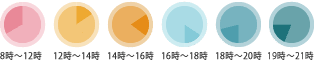- おすすめキーワード
-

<連載>原田和典のJAZZ徒然草 第109回
- JAZZ
- 新着ニュース
2018.10.16
アフリカン・フェスティヴァルから超巨大サックス、「アメリカン・グラフィティ」さながらのミュージカルまで、今年もニューヨークは刺激と興奮がいっぱいだぜ
久々のニューヨーク訪問である。どの土地でもそうだと思うが、ライヴはたいてい夜に行なわれる。では、昼は何をするのか? 夜に備えて仮眠をとるのもいいだろう。しかしせっかくの海外である、高い旅費を払った以上のものを得たいではないか。だからぼくは毎回、全身をギラギラさせながら、何か面白いものはないかと嗅覚を鋭くして野良犬のように動き回っている。
宿に着いて早速MoCADA(モカーダ)こと「ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アフリカン・ディアスポラン・アーツ」(80 Hanson Pl, Brooklyn)に行く。大きめの看板を目指して歩き、縦に長いビルの、入り口向かって左側のスペースに入る。場内は美術館というより、誰かの少し広めのプライベート・ルームという感じ。アフリカ移民の写真、偉大な詩人マヤ・アンジェローのポエムが記されたパネルなどに囲まれて、柔らかなソファに腰を下ろすと飛行機で十何時間運ばれてきた疲れなど吹っ飛んだ気になるから不思議だ。今後、さらに展示物が増えていくのではないかという気がする。また角を曲がったところにはアフリカン・グッズの店「Moshood」(https://afrikanspirit.com/)もある。色とりどりのダシーキや髪飾りを見るだけでも立ち寄る価値はあると思う。次回、事前にからだのサイズを計ったうえで、フィットするダシーキを見つけたいと思っている。
「ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アフリカン・ディアスポラン・アーツ」の窓
没してから早21年、ノトーリアス・B.I.G.がストリートを見つめる
ダンスアフリカ、「ハワード・ギルマン・シアター」のチケットはソールド・アウト
この一帯から5分ほど歩くと、BAM(ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック)が主催している「ダンスアフリカ・フェスティヴァル2018」のエリアにたどりつく。ぼくはここで南アフリカ発祥“ガンブート・ダンス”の初心者コースを受講した。先生のパット・ホール氏は、ウォーレン・スミス(ローランド・カーク、サム・リヴァース、アレサ・フランクリン等と共演経験のある打楽器奏者)と一緒にダンス+フリー・インプロヴィゼーションのツアーを行なったこともあるという。このダンス講座については「ブルース&ソウル・レコーズ」の143号に書いたのでぜひごらんいただきたい。
服は着てみたいと思わせ、食事は食べてみたいと思わせ、楽器は演奏してみたいと思わせ、ようするに予算がいくらあっても足りないという気分にさせるのがアフリカン・グッズ売り場だ(「アルケブラン」という出店もあった。意味は“ランド・オブ・ザ・ブラックス”、パーカッション奏者エムトゥーメイの代表作のタイトルでもある)。それが通路の両脇にズラッと並んでいる。その先には「ハワード・ギルマン・シアター」という劇場があり、ぼくはここで「Remembrance, Reconciliation, and Renewal」という出し物を見た。2部制で所要時間は約2時間半。演出はアブデル・R・サラーム、出演はインゴマ・クワズールー=ナタル・ダンス、シウェラ・ソンケ・ダンス・シアター、BAM/レストレーション・ダンス・ユース・アンサンブル。撮影禁止だったが、撮影OKであってもあの動きと舞いの速さはカメラではとらえられなかったのではないか。キャブ・キャロウェイ風におしゃれした男性の司会進行もスマートだった。
ダンスアフリカに連動した出店やストリート・パフォーマンス
音楽ファンに嬉しい展示も多い「ブルックリン・ミュージアム」(200 Eastern Pkwy, Brooklyn)には展覧会「デヴィッド・ボウイ・イズ」が来ていた。昨年上旬、東京で催されていたものを見逃したので実にうれしく感じた。兄の影響でジャズにハマったこと、サックスを吹いていたことなどにもしっかり触れられていた。また映像コーナーでは「サタデイ・ナイト・ライヴ」出演時のマテリアルも上映されていて(歌に絡むデヴィッド・サンボーンのサックスが、また妖艶なのだ)、ボウイとクラウス・ノミの共演映像にも胸が熱くなった。ノミはぼくにとってオペラ・ロックの神様である。
マンハッタンの「シアター・ロウ」(410 W 42nd St)ではミュージカル「ザ・マーヴェラス・ワンダレッツ」を観た。
最初の舞台となるのは1958年のパーティー。高校の女子生徒たちがこの日のために思いっきりおしゃれをしてヴォーカル・グループを組んで、好きな男の子や憧れの先生のハートを射止めようというプランだ。
服装は映画『アメリカン・グラフィティ』から、そのまま飛び出してきたかのよう。歌われた曲は「ロリポップ」(コーデッツのカヴァー版で流行ったが、もともとは人種混成デュオ“ロナルド&ルビー”の持ち歌)、「ミスター・サンドマン」等。その後メンバーはいろいろあって離れ離れになり、それぞれがそれぞれの経験を積んでいくのだが、10年後の68年に再会、また一緒に歌いはじめる。衣装はガラッと変わり、曲目もアレサ・フランクリンの「リスペクト」、フォンテラ・バースの「レスキュー・ミー」等、いわゆるR&B色の濃いものになる。みんなミュージカル女優だけあって歌のうまさ、表情(顔芸も含めて)は立派だと思ったものの、ストーリー自体、正直言ってそれほど大したものではないという印象を受けた。名曲の力に助けられて最後までとりあえず楽しむことはできたが。
「デヴィッド・ボウイ・イズ」入口
「ザ・マーヴェラス・ワンダレッツ」入口
また「イル・ガットパルド」(13-15 West 54th Street、日本語で言うと「山猫軒」という感じ)というレストランでは、ギター奏者アサフ・ケハティ(Assaf Kehati)とベース奏者マイケル・オブライエンのデュオを聴いた。アサフはイスラエル出身だが、先ごろ傑作『アスク・フォー・ケイオス』をリリースしたギラッド・ヘクセルマンより4歳上(1979年生まれ)、これまでエリ・デジブリ、ドニー・マッキャスリン、シェイマス・ブレイクらと共演、リーダー作もすでに3作品出している。そこではオリジナル曲中心だったが、このレストランではモダン・ジャズに根付いたスタイルで「セント・トーマス」、「ムーン・アンド・サンド」、アントニオ・カルロス・ジョビンの「ジンガロ」等を味わわせてくれた。
モダン・ジャズといえば、60年代にボビー・ティモンズらと共演、70年代にはアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの一員としても働いた(当時のトランペット奏者はウディ・ショウ)ベース奏者ミッキー・バース(初期はLee Otis Bass IIIと名乗る)も元気だった。バンド名は“ニューヨーク・パワーハウス・アンサンブル”、場所はハーレム近くの「フェゾン・ファイアーハウス・シアター」(6 Hancock Pl,)地下だ。他のメンバーはジョン・エッカート(トランペット)、ブレント・バークヘッド(アルト・サックス)、トミー・モリモト(テナー・サックス)、スティーヴ・ネルソン(ヴィブラフォン)、マーク・ジョンソン(ドラムス。Mark Johnson)。ピアノの不在を補って余りあるネルソンの4本マレット・プレイが見事、ふたりの若手サックス奏者も燃えに燃えていた。
特にMs.ローリン・ヒルのバックで来日経験のあるブレントの4ビート・プレイの、なんとかっこいいこと! 師匠チャーリー・ヤング(現デューク・エリントン楽団のコンダクター兼サックス奏者)の薫陶を大いに受けたのだろう。ミッキーのベースはアンプの音量の上げすぎ、グリッサンドのしすぎという感じがしたが(もっとも70年代以降のアルバムを聴けばわかるように、彼はアンプで音を創るタイプの奏者であるのだが)、曲作りのセンスには恵まれている。全曲彼の自作で、メッセンジャーズや、キャノンボール・アダレイやホレス・シルヴァーのバンドへの敬意をうまく現代的に、ポップにしたようなメロディ・ラインには文句なしに惹かれた。
アサフ・ケハティ
「フェゾン・ファイアーハウス・シアター」外観
ミッキー・バース
ローリン・ヒルのバックで来日経験あり。
ハード・バップを吹いても素晴らしいブレント・バークヘッド
今年で23回目を迎えた「ヴィジョン・フェスティヴァル」についてはジャズジャパン誌の96号で触れたが、誌面の都合で不採用になった画像があるのでここに紹介したい。スコット・ロビンソンが吹くコントラバス・サックスという楽器だ。ぼくはかつてアンソニー・ブラクストンが脚立に乗ってこれを演奏するライヴを体験したことがあるが、スコットが持っているのはそれよりも大きく見えた。20世紀の初めに造られて、いまや世界に1,2台しかないという。彼自身おそらく190センチはあろうかという大柄なひとなのだが、それが遥か小さく見えてしまうほど楽器が大きい。
それにしてもスコットの多様性はすごい。最近ではドラムの若き名手ルイス・ケイトーがボカンテのベース奏者として何食わぬ顔で凄さを発揮していたり、ジェイコブ・コリアーのように歌、キーボード、ギター、ベース、ドラム、打楽器ぜんぶこなしてしまうとんでもない逸材も出ている。が、各種トランペットと各種サックスを奏で、ラグタイムから現代音楽まで横断し、もう解散してしまった秋吉敏子=ルー・タバキン・ビッグバンドから現役バリバリのマリア・シュナイダー・オーケストラまで数々の名門大所帯に呼ばれ、いざリーダー作ではホット・ファイヴ時代のルイ・アームストロングへのトリビュートなどもしてしまうスコットの多彩さ・柔軟さには年季が入っている。ぼくが「ヴィジョン」で見たときはロスコ―・ミッチェルとバリトン歌手トーマス・バックナーを中心とする“スペース”への参加(山下洋輔を通じて麿赤兒の大駱駝艦とも交流のあった故・ジェラルド大下の後任)で、非常に抽象的だが実に聴きごたえのある音楽を展開。約50分のセットのなかでスコットは両手以上の数の楽器を操り、キメ技を決めるようにコントラバス・サックスにしがみついてすさまじい重低音を鳴らした。「体長5メートルのヒキガエルが食べ飲み放題に行ってたらふく胃袋をふくらませ、もう食えないとあきらめたときに発するゲップって、こんな感じなのかな」と思いながら、ぼくは改めてスコットの肺活量に感服した。
スコット・ロビンソンと彼のコントラバス・サックス
トロンボーン奏者として知られるクレイグ・ハリスの愛用するディジリドゥー
駅に張られていた広告。カマシ・ワシントン、カルチャー・クラブ、ロジャー・ダルトリー、マックスウェル、ロバート・プラント等。この混ざり具合が「現代」だ
グリニッチ・ヴィレッジ猫
最新ニュース
-
2024.04.25
- JAZZ
-
2024.04.25
- JAZZ
-
2024.04.24
- JAZZ
<予約>ジャイルス・ピーターソンお墨付き!フランク・ノヴィエロのデビュー作「Surprise!」が《JAZZ ROOM RECORDS》より初再発
-
2024.04.24
- JAZZ
-
2024.04.24
- JAZZ
<予約>リロイ・ヴィネガーの1973年作:レア・グルーブ・ファンにお薦めの名作「Glass Of Water」が初のLP再発!!
-
2024.04.24
- JAZZ
-
2024.04.24
- JAZZ
【CD入荷】<予約>韓国のジャズ・ディーヴァMOONと山本剛トリオによるスタンダード作品「Midnight Sun」発売決定
-
2024.04.24
- JAZZ
SHAG(SUGIZO) 、エメット・コーエンと共演するサックス奏者パトリック・バートリー、井上銘らと結成したバンドのデビュー作が完成
-
2024.04.24
- JAZZ
-
2024.04.24
- JAZZ