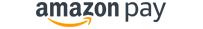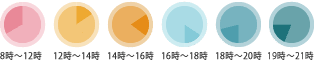- メンバーズ登録 /
- ウォントリストを見る /
- ご利用ガイド /
- よくあるご質問 /
- Shipping
- おすすめキーワード
-

<連載>原田和典のJAZZ徒然草 第103回
- JAZZ
- JAZZ徒然草
2017.07.28
ホーギー・カーマイケルやグレン・ミラーや李香蘭のファンも必見!
1939年の上海租界を舞台にした音楽劇『魔都夜曲』が、ノスタルジックで妖艶なジャズの世界に案内してくれるぜ
音楽劇『魔都夜曲』より 撮影:桜井隆幸
●ミュージカルとはまた一味異なる、音楽を使った劇を見てみたい人
●スタンダード・ソングやスウィング・ジャズに関心のある人。ジャズメンの生演奏が好きな人
●川島芳子、李香蘭、甘粕正彦といった名前に心のトキメキを覚える人
この3つのどれかに心当たりがあるなら、何を差しおいても見てほしい。それがcube 20th. presents音楽劇『魔都夜曲』(まとやきょく)だ。
ぼくは上記3項目すべてにひっかかり、しかも西木正明の柴田錬三郎賞受賞作「夢顔さんによろしく」も読んでいたので、物語の進行を追うのにわくわくしてしようがなかった。
7月29日まで東京・Bunkamuraシアターコクーンで上演され、その後、8月5日と6日には愛知・刈谷市総合文化センター アイリス、8月9日から13日までは大阪・サンケイホールブリーゼを舞台に行なわれる。原作・脚本はマキノノゾミ、演出は河原雅彦。
音楽劇『魔都夜曲』より 藤木直人(白川清隆役)とマイコ(周紅花役) 撮影:桜井隆幸
ネタバレ厳禁ということで進めさせてもらうが、物語の舞台が「1939年の上海」、しかも「ル・パシフィーク」なるジャズ・クラブのシーンもふんだんに登場する。租界とジャズの蜜月。よって妖しい雰囲気が、劇中、むんむんとたちこめる。物語が本格的に始まる前には生バンドがインストゥルメンタルでジャズを演奏する箇所もあり、木幡光邦をはじめとする名手たちがくつろいだアドリブを聴かせた。木幡は“高橋達也と東京ユニオン”で名をあげ(ぼくはこのビッグ・バンドで彼のプレイを初めて聴いた)、小曽根真No Name Horses、守屋純子オーケストラ、自身のKUNIZO BIG BANDやホット・コルネッツなどでも活動するベテラン。この音楽劇ではトランペットではなくコルネットを吹き、曲によってはギター演奏も披露した。コルネットとギターを両方こなす奏者など、ほかに元グレン・ミラー・オーケストラのボビー・ハケットぐらいだろう。
ホット・コルネッツ『オール・オブ・ミー』
ジャズ・クラブの名司会者、陽気なボーイは、“サミー”という名前。アフリカ系アメリカ人の血が入っているようだが、故郷は日本だ。ちょっとダミ声のヴォーカルは達者そのもの、酔客からは「ニューオリンズに生まれていたら、ルイ・アームストロングみたいになってたんじゃないか」との声も飛ぶ。ルイを思わせる声と、キャブ・キャロウェイ風の派手な動きは、ジャズ・ファンの心にもしっかり刺さるはずだ。
ルイ・アームストロング『ハロー・サッチモ!』 | キャブ・キャロウェイ『キャブ・キャロウェイ』 |
「ル・パシフィーク」は生演奏も聴かせる店だが、ライヴのない時は蓄音機でジャズ・レコードをかけている。ある日、一枚の新譜が持ち込まれた。アメリカで人気絶頂、グレン・ミラー・オーケストラの「ムーンライト・セレナーデ」である。バンドマンはかつて聴いたことのないようなクラリネット入りの斬新なハーモニーに驚き、ほかのひとたちは美しいメロディに酔いしれている。
こんな風景、きっと実際にあったはずだ。そしていろんなところでジャム・セッションが繰り広げられていたかもしれない。39年にさかのぼること数年前の1934年ごろには、バック・クレイトン(トランペット)がアメリカから上海に渡っている。このクレイトンはもちろん、30年代後半にカウント・ベイシー・オーケストラの花形奏者となる、あの名手と同一人物だ。
日本のジャズメンが上海に渡るようになったのは大正時代の末期からと伝えられる。平茂夫(日本のジャズ・ピアニストの草分けで、ザ・ドリフターズの加藤茶の叔父でもある)は「ジャズの本場は上海」と言い、1929年(昭和四年)には南里文雄(トランペット)が数か月滞在した。このとき、ルイ・アームストロングとも共演したことのあるアメリカ人のピアノ奏者テディ・ウェザーフォードと知り合い、指導を受けたことで彼の演奏は長足の進歩を示したといわれる。35年には歌手の水島早苗(大橋巨泉の最初の夫人であるマーサ三宅や、水森亜土の師匠でもある)も上海に行った。
ここで「別冊一億人の昭和史 日本のジャズ」(毎日新聞社)に掲載されているサックス奏者、大川幸一(明治43年生まれ)の述懐をひいてみたい。しかも『魔都夜曲』の前年にあたる1938年7月に渡航しているのだ。ざっと気になる箇所に触れると
●バンド9人+歌手1人で北四川路のブルーバード・ダンスホールに出演
●上海事変の直後で、日本人租界は戦禍で無残な姿だったが、それでも表通りには数々のダンスホールが開店しており、商工や軍属の客でにぎわっていた
●それよりも盛り上がっていたのは南京路(フランス租界)のほう。演奏を終えるとそこに遊びに行き、いろんなギャンブルも楽しんだ
●日本円は価値が高く、ギャラも良かった。当時のバンドマンにとっては、上海は天国のような楽天地だった
誌面にはさらに、長谷川一夫と李香蘭と一緒に大川氏が映った写真も掲載されている。キャプションには、映画「上海の月」のロケのときに撮影されたものであるように書かれているが、資料を参照すると同作品は41年7月の東宝系公開作品で主演は山田五十鈴、とある。ぼくは残念ながら見たことがないけれど、調べたところによると現存するフィルムは半分の長さしかないらしい。そして長谷川や李香蘭が出ているという情報はどこにもない。となるとやはりこの写真は、いわゆる大陸三部作『白蘭の歌』『支那の夜』『熱砂の誓ひ』のロケ中のどこかで写された、と考えるのが無難か。天下の二枚目スタアと、日劇(※日本劇場。当時、絶大なステイタスがあった。今でいうところの日本武道館に匹敵しよう)コンサートで建物を七周半するぐらい多くのファンを集めた歌姫、そしてさすらいのジャズマン。実に味わい深い3ショットである(実際は後列にも4人写っているが)。
李香蘭『伝説の歌姫 李香蘭の世界』
李香蘭については、2015年に出た2枚組CD『伝説の歌姫 李香蘭の世界』がマスト・アイテムだろう。戦後は本名の山口淑子を名乗り、一時期は日系アメリカ人彫刻家のイサム・ノグチと結婚していたこともある。ぼくはイサムの作風も大好きなので、先日ニューヨークに行ったときはロング・アイランドまで足を延ばして「イサム・ノグチ美術館」(The Noguchi Museum)を訪ねて“石の芸術”に酔いしれた。ふたりはチャールズ・チャプリン(もちろん、あの俳優で映画監督の)のパーティで出会い、イサムのほうが先に惚れてしまったのだという。イサムと山口の結婚生活については彼らを題材にした数々の本で触れられていることと思うが、『魔都夜曲』に登場するのはそれよりもずっとずっと前の、うら若き李香蘭だ。彼女は1920年生まれだから、39年の時点で19歳。『魔都夜曲』では東京パフォーマンスドールの高嶋菜七と浜崎香帆が交互に演じているが、現在のふたりは、ほぼ当時の李香蘭と同年代にあたる。
ぼくが見たときは、浜崎が李香蘭役に扮していた。ジャズ・バンドのピアニストが、片思いの女性に捧げてとても美しい曲を書く。それを周りから歌ってみてと勧められ、ほとんど譜面初見状態のまま、そのピアニストの伴奏で歌いこなす・・・という大きな見せ場もある。
この浜崎が「新境地開拓」と太文字で書きたくなるぐらい新鮮な魅力を放っていた。もともと歌唱力には定評があり、東京パフォーマンスドールの音楽面の要のひとりといえる存在ではあったのだが、役を演じるにあたって発声から根本的に変えた(というか李香蘭になりきった)のだろう、流れるようなソプラノ・ヴォイスで、グリッサンドやポルタメントも利かせつつ、文字通り機(はた)を織るように“夜曲”を歌いあげていた。
 音楽劇『魔都夜曲』より。 浜崎香帆(李香蘭役;ダブルキャスト)の歌唱シーン 撮影:桜井隆幸 |  音楽劇『魔都夜曲』より。 高嶋菜七(李香蘭役;ダブルキャスト)の歌唱シーン 撮影:桜井隆幸 |

M’BOOMを思わせる打楽器アンサンブル、アレサ・フランクリンのファンにもおすすめの楽曲「PEOPLE」、アカペラ歌唱など、見どころ・聴きどころ満載。東京パフォーマンスドールの映像作品『東京パフォーマンスドール ダンスサミット“DREAM CRUSADERS"~最高の奇跡を、最強のファミリーとともに!~ at 中野サンプラザ 2017.3.26』(8月2日リリース)
その李香蘭と交流があったと伝えられる川島芳子も、劇中にスパイスを加えている。別名“東洋のマタハリ”、今ではちっとも不思議じゃなくなった「ぼくという一人称を使う女子」の草分けでもあったようだ。彼女は一時期、李香蘭と同じく日本コロムビアからレコードを出していた。2011年リリースのオムニバスCD『伝説を聴く』には「十五夜の娘」という曲が収録されている。蒙古民謡をみずから日本語に訳して歌っているのだが、“十五夜お月様 まあるいね ハホーイ”という能天気(?)な歌詞と、あのキリッとした容姿が自分にはどうしても結びつかず、またそれがなんともいえない味わい深さへとつながる。

オムニバス『伝説を聴く』(川島芳子の歌唱入り)
書いているうちに文章が少しずつジャズから離れてしまった。最後に、『魔都夜曲』の劇中にはいくつものジャズ・ナンバーが挿入されていることにもしっかり触れておきたい。「スターダスト」や「ジョージア・オン・マイ・マインド」で語られがちなホーギー・カーマイケルの他の曲の魅力についてもたっぷり知ることができるはずだし、アーヴィング・バーリン作のあの曲がこんなところで使われて効果をあげているぞ、という発見を得ることもできるだろう。大ヒット映画『ラ・ラ・ランド』でミュージカルに関心をもつ層が激増したように、『魔都夜曲』を見てジャズのノスタルジックな側面に引き付けられるオーディエンスも多いのではないだろうか。この音楽劇は、「ジャズはどんなアングルからも楽しむことが可能なのだ」というこちらの勝手な考えを、実に快く裏付けてくれた。

ホーギー・カーマイケル『ホーギー・シングス・カーマイケル』
cube 20th. presents
音楽劇『魔都夜曲』 公式サイト (https://cube-s.wixsite.com/matoyakyoku)
最新ニュース
-
2024.08.15
- JAZZ
-
2024.05.13
- JAZZ
-
2024.04.09
- JAZZ
-
2023.11.21
- JAZZ
-
2023.07.20
- JAZZ
-
2023.04.25
- JAZZ
-
2022.11.24
- JAZZ
-
2022.06.14
- JAZZ
-
2022.05.11
- JAZZ
-
2022.01.19
- JAZZ