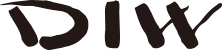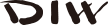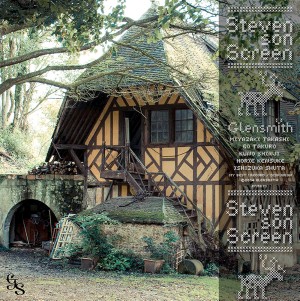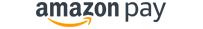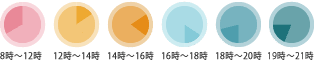- メンバーズ登録 /
- ウォントリストを見る /
- ご利用ガイド /
- よくあるご質問 /
- Shipping

「ポール・マッカートニー/ヴァラエティ 連載No.42」 宮崎貴士
- DIW PRODUCTS GROUP
- ニュース
2021.03.08

【レノン=マッカートニーについて Vol.2】
前回、〝エルヴィス・プレスリー〟を媒介にして共鳴した二人、ジョン・レノンとポール・マッカートニーの出会いについて記した。エルヴィスの存在感と歌唱力、50年代後半から60年代初頭にミドルティーンだったジョンとポールにとって、当時圧倒的な人気を誇っていたエルヴィスは憧れ対象(アイドル)であったと思う。ただし、ジョンとポールの二人はシンガーでもありながら同時に追求していたのはソングライターとしての自分たちの可能性である。
後追い世代にとって〝ザ・ビートルズ〟の音楽性とソロ・シンガー〝エルヴィス・プレスリー〟の存在感に連続性をさほど感じられない理由があるとしたら、それは《ソングライターとしての意識》が楽曲に反映されているかどうかの違いがあるのではないか。自分が知識を持ち合わせていないエルヴィスについての論考をここで深めることは困難だが、ビートルズは初期のアルバムやステージでは(あえて)、エルヴィスの存在から距離を置こうとしているようにも伺えるのだ。ビートルズ時代にはエルヴィス印のイメージがある楽曲を公式には取り上げていないのである(エルヴィスが歌っていた曲を取り上げる時も、原曲アーティストのアプローチを前提にカヴァーしている)。
研究対象というより別格的なシンガーとして憧れていたエルヴィス、そして自作自演のバンドを目指していたビートルズとの距離感。器用であるポールなどはエルヴィスの歌唱法を身に付けているが、エルヴィスの存在感から逃れられない曲はカヴァー対象とするには不適格であるという判断があったのだと想像出来る。物まね以上の何かを表現出来る自信がやはりなかったのだと思う。その判断、憧れ対象との距離感の適切さこそが重要なのだ。
ちなみにポールは2000年代になってから(アイドル)エルヴィスへの愛情をストレートに表現するようになる。
※)参考映像1【Paul McCartney with Elvis Presley Band in Memphis in 2001】https://youtu.be/GElQdbI1_T8
※)参考映像2【Paul sings 'Heartbreak Hotel' with Bill Black's Bass】https://youtu.be/Lgc6Brz4zgM
※)参考映像3【Paul McCartney All Shook Up】https://youtu.be/o5g9nt1wVMA
(映像3でのグルーヴ感、それを可能にしたバックメンバーの力量。年齢を重ねたポールの「今なら自分流の解釈で演奏出来る」という確信が感じられる)
〝レノン=マッカートニー〟の意識には「歌う自分」が常に意識化されている。それが特別なのだ。
※)参考映像4【Long Tall Sally (Remastered 2009)】https://youtu.be/w-iA9-D_Mbw
ビートルズ時代、ポールが歌うもっとも有名なカヴァー・ソング。自分の歌として歌える曲であることがやはり前提なのだ、ジョンもしかり。その曲を歌うことでシンガーとしての能力を拡張させられること、その歌唱力が(オリジナリティ)として確立していること。レノン=マッカートニーがビートルズ時代に選んだカヴァー・ソングを聞けば、二人にとっての楽曲の捉え方とシンガーである前提が不可分な領域であったのが理解出来る。
あえてエルヴィス印の曲を取り上げなかったからこそ、彼らのオリジナリティは担保されていたのだ。
ジョンとポールは突出した歌手でもあり、バンドの一員として楽器も演奏する。《作詞家と作曲家》または《歌手と楽曲制作チーム》、他のソングライターチームのように分業制であったなら解散以後でもジョンとポールが再び組む可能性はあったかもしれない。が、二人にとっての曲作りは演奏や歌唱も含めた全方位型の(融合)の結果であって、互いの領分を明確に分業化した関係ではなかったのだ。そして当然、『ザ・ビートルズ』の音楽になるには、リンゴ・スターとジョージ・ハリスンの存在、バンドのグルーヴが必要なのである。
常に(歌い手)としても互いの曲に介入する、ここが他のソングライターチームと〝レノン=マッカートニー〟の決定的な違いである。歌手として楽曲を表現するということはその曲の感情表現をも手にするという意味である。その曲が書かれた背景、状況含め、相手の曲にすべての段階で介入していたからこそ、二人はもつれた感情的な関係からも逃れることは出来なかった、と想像してしまうのだ。
特に私生活の感情をストレートに楽曲に結びつけるジョンにとっては創作は日常の延長である。同じ時間を過ごし、同じ目的を共有した上で膝を付き合わせ、互いに歌いあって曲を作り上げる。ビジネス上の意識だけで出来る作業、その関係ではなかったからこそ、解散以後のコンビの復活は困難であったのだと思っている。
そのクリエイティブな意識をバンド内でチームとしても維持していたからこその〝レノン=マッカートニー〟だったのである、二人の責任感によってザ・ビートルズは維持されていた。安易な選択をすることなく互いに牽制しあいつつ妥協せずに先に進むこと。
ザ・ビートルズ時代に選んだカヴァー・ソングの数々もチームであったからこその批評的かつ意識的な行為だったのである。
そしてビートルズ時代では解体も再構築もしなかった(出来なかった)対象であったという事実こそ、『エルヴィス・プレスリー』が彼らにとって最大のアイドルだったことの逆証明にもなるのである。
他、曲提供、編曲、など多数。ライター活動としては「レコード・コレクターズ」(ミュージック・マガジン社)を中心に執筆。直近では2020年9月号のレコード・コレクターズ「ポール・マッカートニー・ベスト・ソングス100」特集号にて執筆。
宮崎貴士[mail : m-taka-m@da3.so-net.ne.jp]
最新ニュース
-
2024.07.24
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2024.07.19
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2024.04.30
- DIW PRODUCTS GROUP
「とらドラ!」BESTアルバム「√HAPPYEND」LPレコード化を記念して、オーディオユニオン新宿店にて視聴会を開催!
-
2024.04.19
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2024.01.09
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2023.11.01
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2023.02.23
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.12.27
- DIW PRODUCTS GROUP
-
2022.04.14
- DIW PRODUCTS GROUP
MOUNT MOUTH & THE SKA-MANS Shuffling : Maskman Ska(7インチ)発売延期のお知らせ
-
2022.03.15
- DIW PRODUCTS GROUP