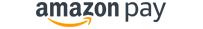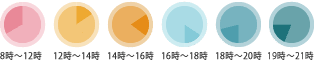- おすすめキーワード
-

<連載>原田和典のJAZZ徒然草 第121回
- JAZZ
- JAZZ徒然草
2022.05.11
「ニューポート・ジャズ祭」にも登場した名歌手・弘田三枝子の6枚組CD+DVDボックスが登場。こういう時代だからこそ、「パンチの利いた歌声」に目いっぱい打たれてみたいぜ

新型コロナウィルスの蔓延から、もう3年目になる。さすがに今年は外国人ミュージシャンの来日が増加傾向にあり、客席の50%がライヴ収容の上限ということもなくなってきた。マスク着用のうえ検温や消毒に協力していれば、とりあえず日々のモロモロはつつがなく過ぎるようになってはきた。コロナ禍以降、皆さんはおそらく「聞き取る力」と「読み取る力」が著しく伸びたのではなかろうか。ぼくも個人的にそれを感じている。端的にいえばマスク越しに相手がしゃべっていることを捉えるための耳の能力が増し、両目の下の、たとえば以前なら笑顔の時に見えていたであろう歯などのファクターがなくても、相手の目の細め方や大きくし方を見ることによって、その人がどの程度、嬉しがっていたり楽しんでいたりしているのかなども測れるようになってきた。こうして生き物はアップデイトされていくのだ。
コロナ蔓延元年の2020年は、本当に多くのひとたちをこの世から奪い去った。コロナが原因の方もそうでない方も、多数の方がいなくなった。今回ご紹介する弘田三枝子もこの年の7月21日に亡くなっている。60年間に及ぶ現役活動中に残した多数の作品をオリジナル盤で集めることは不可能に近いのではないか(とくに60年代のアイテムたるや、シングル盤、10インチLP、12インチLP、コンパクト盤、ソノシートが混在していて、すさまじい)。三回忌ということもあるのだろう、この2月23日には、CD6枚+DVDボックス『弘田三枝子・プレミアム』がリリースされた。ディスク1から3は「シングルズ」、ディスク4はそれ以外の洋楽カヴァー中心、ディスク5は洋楽カヴァーや日本語詞曲で構成されていて(「シェーク・アンド・ロール」のR&Bフィーリングは鳥肌もの)、ディスク6は「アスパラで生き抜こう」などのCMソングや大ヒット「人形の家」の英語ヴァージョンなども含むレアリティーズ集、そしてDVDには紅白歌合戦での歌唱などが収められている。特にジャズファンにとって嬉しいのは古典的一枚『ニューヨークのミコ ニュー・ジャズを唄う』からの曲や、菊地雅章や渋谷毅のアレンジ曲が入っていること。入手してからずっと、ぜひ取り上げたいと思っていたのだが、全138曲収録というすさまじいボリュームであるし、弘田三枝子のパンチのある歌は聴き流すには手ごたえがありすぎるので、じっくり味わっていたところ、発売からずいぶん遅い紹介執筆になってしまったのである。
弘田三枝子は中学1年生の頃から米軍キャンプで研鑽を積んだ後、60年7月にテレビ番組「ヒット・キット・ショー」のオーディションでアーヴィング・バーリン作「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」を歌って合格。61年11月に東芝音楽工業からデビュー・シングル「子供ぢゃないの」を発表した。当時の東芝には梅木マリ、ベニ・シスターズ、香山ユリ、斎藤チヤ子、富永ユキ、少しおねえさん系では朝丘雪路などガール・ポップスの宝庫という印象があるのだが、個人的には、あの、なんともいえない隙間感が愛おしい東芝モノラル・サウンドに弘田三枝子の歌声は分厚すぎるのではないかと思うこともしばしばだ。もっともモノラルなのはシングル盤だけで、10インチLP『弘田三枝子 スタンダードを唄う』(63年)あたりはステレオ盤も出ているのだが、自分にとっての彼女の醍醐味は、64年の日本コロムビア移籍以降のステレオ録音による、ごく自然な広がりのある伴奏トラックと、パンチの利きを維持しつつも押しと引きを絶妙に心得るようになった歌声の数々だ。『弘田三枝子・プレミアム』ではディスク1の13曲目「はじめての恋人」からコロムビア音源が始まる。発表は64年12月、ということは、コロムビア史観でいくと、その前月にあたる11月には美空ひばりが「柔」、さらにその前月の10月には都はるみが「アンコ椿は恋の花」を出している。つまり演歌のメガ・ヒットが出まくっていたときに、ポップス・シンガー弘田三枝子は他社からひょっこりやってきたことになる。
自宅には1000枚ものレコードがあり、雑誌のお部屋訪問的口絵にはエラ・フィッツジェラルド&ネルソン・リドル『エラ・スウィングス・ブライトリー・ウィズ・ネルソン』、ダイナ・ワシントン『アフター・アワーズ・ウィズ・ミスD』、オスカー・ブラウンJr.『ビトウィーン・ヘヴン・アンド・ヘル』、アーネスティン・アンダーソン『モーニン・モーニン・モーニン』、レイ・チャールズ『ジニアス・ヒッツ・ザ・ロード』等のジャケットが見える。その歌唱は、62年に来日したキャピトル・レコードのスタッフにも称賛されたとのことだし、64年には渡米してミュージカルを勉強したり作曲家ジミー・マクヒュー(「オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート」等を書いた)に会う予定もあったようだが、実際のところ、まだ敗戦から十数年ほどの日本では、どの程度、確かだと保証できる海外進出プランが存在したかどうかはわからない。が、アメリカで歌唱するチャンスは突如、おそらく最上といえる形でやってきた。
昨年9月に93歳で亡くなったプロモーター、ジョージ・ウィーン------「ストーリーヴィル」と名乗るジャズ・クラブやレーベルを率い、長くニューポート・ジャズ・フェスティバルのブッキングに関わり、スウィング・ジャズ系ピアニストとしても数々のアルバムを残す人物だ。映画『真夏の夜のジャズ』の舞台となった1958年度のニューポートにも当然ながら全面的に関わっていたのだが、おそらく意図的に名前のクレジットが外されるという忸怩たる思いも経験している。彼が自らブッキングに関与した「第1回世界ジャズ・フェスティバル」(第2回以降はなかった)のため、マイルス・デイヴィス・クインテットをはじめとする錚々たる音楽家たち、評論家レナード・フェザーなどと共に初めて日本の土を踏んだのは東京オリンピックの年、64年夏のこと。ウィーンは日本に大きなビジネスの可能性を感じたのだろう、65年1月、今度は「第二回ドラム合戦」というコンサートの責任者として再来日した(ドラマーはフィリー・ジョー・ジョーンズ、チャーリー・パーシップ、バディ・リッチ、ルイ・ベルソン)。どうやら、この訪日はニューポートに日本人ミュージシャンを招聘するためのスカウトを兼ねたものでもあったらしい。ウィーンはオーディション(弘田三枝子ひとりのために行なわれたのか否かは不明)で三度にわたって彼女の歌(「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」等)をテストし、「まだ英語に難はあるが、大物になる素質あり」とニューポート行きを認めた。
彼女がアメリカ本土に到着したのは6月下旬とされる。ステージは7月3日が本番だったが、少なくとも、前日の2日にはロードアイランド州ニューポートの野外特設会場に顔を出していた。というのもセロニアス・モンクに挨拶し(モンクの国内盤新譜は当時、日本コロムビアから出ていた)、ジョン・コルトレーンと記念撮影をしているからだ。コルトレーンとの写真には和服のもの(コルトレーンは弘田の肩に手をかけている)と洋装のものがある。どこかのタイミングで着替えたということなのだろうが、その間、コルトレーンがじっと待っていたのかと思うとなんだか微笑ましい。
ここで65年度ニューポートの主な出演者を、当時のパンフレットからひいておく。
7月1日(初日) メンフィス・スリム、ピート・シーガー、マディ・ウォーターズ・ブルース・バンド(ジェイムズ・コットン参加)、ディジー・ガレスピー、レス・マッキャン、ジョー・ウィリアムスなど
7月2日(昼の部) ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ、アーチー・シェップ、ポール・ブレイ、セシル・テイラー
7月2日(夜の部) アート・ブレイキー、カーメン・マクレイ、マイルス・デイヴィス、セロニアス・モンク、ジョン・コルトレーン
7月3日(昼の部) ドラム・ワークショップ:ルイ・ベルソン、アート・ブレイキー、ロイ・ヘインズ、エルヴィン・ジョーンズ、(パパ・)ジョー・ジョーンズ、ジョー・モレロ、バディ・リッチ
7月3日(夜の部) ジャム・セッション(イリノイ・ジャケー、秋吉敏子、トニー・スコット他)、弘田三枝子、デイヴ・ブルーベック、ハービー・マン、アール・ハインズ、デューク・エリントンfeatルイ・ベルソン
7月4日(昼の部) デニー・ザイトリン、ウェス・モンゴメリー+ウィントン・ケリー、アッティラ・ゾラー、ダラー・ブランド、スタン・ゲッツ
7月4日(夜の部) オスカー・ピーターソン、カウント・ベイシー+フランク・シナトラ
ヨダレがこぼれそうなほどすごいメンツだ。弘田三枝子は会場でエリントン、カーメン等のパフォーマンスを満喫したらしい。なんたるうらやましさ。もしニューポート入りが早まって7月2日昼のステージを目の当たりにしていたら、帰国後、日本初のフリージャズ歌手になるという、別の道が開けていたかもしれないとも妄想してしまう。
65年度ニューポートには、評論家の本多俊夫(サックス奏者・本多俊之の父)や、カメラマンで後年ベーシストとして認められる中村照夫なども足を運んでいたはずだが、ぼくの知る中で弘田三枝子のステージを詳細にレポートしているのは原田信夫(ムード歌謡グループ“ザ・キャラクターズ”のリーダー。原信夫とは別人)だけだ。弘田は大雨がやんでから登場し、「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」、メモを見ながらの英語のあいさつ、「ミスティ」、「ムーン・リヴァー」、「マック・ザ・ナイフ」、前田憲男アレンジの「三階節」を聴かせた。現場を捉えたカラー写真を見ると当日の弘田はピンク色のドレスを着て、すごく嬉しそうな表情をしている。一部で“スタン・ゲッツ楽団が伴奏予定”と報じられていたものの、当日のサポート陣はビリー・テイラー(ピアノ)、ベン・タッカー(ベース)、グラディ・テイト(ドラムス、現場写真ではバスドラに“BR”とのイニシャルがある。バディ・リッチの楽器を使ったのか)、ほかトニー・スコット(クラリネット)も加わったようだ。いわゆる進駐軍として日本滞在の経験があるはずのタッカー、一時期日本に住んでいたスコットの存在は弘田に大きな安心感を与えたことだろう。日系二世のパット鈴木を別にすれば、日本人のニューポート参加は秋吉敏子(56年初登場)に続いて、二人目だったのでは。67年にはビッグ・バンド“原信夫とシャープス&フラッツ”、68年には渡辺貞夫が単身で登場している。そのときサポートしたのもビリー・テイラーだった。
ニューポート出演を終えた弘田三枝子は、ニューヨークに向かう。アルバム・レコーディングのためだ。日本の流行歌手は当時、あくまでもシングル盤第一主義で、アルバムが出たとしてもそれはシングル集的なものが多かった。そんな時代に、アルバム単位の吹き込みが、しかもニューヨークで実現したのは、いくら実力のある歌手だとしても奇跡的なことではないか。銭湯入浴料28円だった頃、1ドル360円だった頃の話なのだ。

7月5日から、弘田はベン・タッカーのレッスンを受けた。「本物のジャズをつかみなさい」と、ユセフ・ラティーフのリハーサルに連れていかれたこともあるようだ。伊藤貞司(マヤ・デレンの夫で、打楽器奏者としてハービー・マンと共演。死後、ジョン・ゾーンのTzadikレーベルから作品リリース)とも知り合った。レコーディングのディレクターは、クインシー・ジョーンズお気にいりのピアニストで、ビートルズやハーブ・アルパート&ティファナ・ブラスがとりあげた「ア・テイスト・オブ・ハニー(蜜の味)」の作者であるボビー・スコットが務めた。ほか、コーディネイターとして、当時ニューヨークにいた宮田英夫も協力した。宮田ハーモニカで有名な宮田東峰の子息で、70年代に菊地雅章や日野皓正などのバンドでサックスを吹いた彼の若き日の姿である。
収録は、フィル・スペクターとレスター・シルのレーベル“フィレス”のニューヨーク録音分によく使われたミラ・サウンド・スタジオで行なわれた。ぼくは“日本コロムビアの商品なのだから、米国コロムビアが誇るマンハッタン30丁目スタジオが使われたのだろう”と勝手に思っていたのだが。『ニューヨークのミコ ニュー・ジャズを唄う』という標題はなかなか意味深で、いわゆるスタンダード・ナンバーは含まれていない。日本語一切なしの英語オンリー、曲数は全8トラックと少なめで、歌詞の出てこない(スキャットだけの)曲もある。とにもかくにも、この作品は、英語が母国語ではないものの子供の頃から英語の歌に親しんできた弘田が、限られた日数の中で精一杯取り組んだ努力の証だ。
同アルバムがいま改めて評価されているのは、おそらく世界最初に「サニー」や、ビリー・テイラー作「アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー (ハウ・イット・ウッド・フィール・トゥ・ビー・フリー)」のヴォーカル・ヴァージョンを収録したこととも関係するのだろう。その後「アイ・ウィッシュ~」はニーナ・シモン(67年)、ソロモン・バーク(68年)、マリーナ・ショウ(68年)らによって歌われ、公民権運動の代名詞的ナンバーと言えるほどの支持を集めていく(近年、アンドラ・デイも歌った)。だがそれらも弘田が録音した後の出来事だ。いっぽう、ボビー・ヘブが書き、彼自身の歌によって66年に大ヒットすることになる「サニー」は、ベン・タッカーが仕掛け人となって世に出た一曲といえる。タッカーの談話を紹介したい。
“ハービー・マンのバンドでグリニッチ・ヴィレッジの「ヴィレッジ・ゲイト」に出ているときにボビー・ヘブがやってきた。“君が作った「カミン・ホーム・ベイビー」は僕のレパートリーの一つなんだ。セカンド・アヴェニューのライヴ・スポットで歌っているから聴きにきてよ”というので、その近所に住んでいたし、ふらっと聴きに行ったら素晴らしかった。そこで私は“君の曲も聴きたいな”と言ったところ、彼は「サニー」を歌い出した。最高だった。翌日、マーキュリー・レコーズに彼を連れて行って、(当時マーキュリーの音楽監督的存在のひとりだった)ボビー・スコットに引き合わせた”。
実のところは、タッカーとヘブが出会い、マーキュリーがゴーサインを押すまでに数カ月が流れている。その間に「サニー」をレコーディングしたのは弘田三枝子だ。“彼女自身が楽曲リストの中から選んだ”という、いかにも伝説になりそうな話もあるようだが、実際はタッカーの知り合いの音楽出版社が持っている(おそらく)安くて、まだあまり注目されていない曲のリストの中から、タッカーが強く推したのではないか、というのが個人的な推測だ。
68年2月、弘田は二度目のアメリカ修行をおこない、ロサンゼルスの「ココナッツ・グローヴ」でマーヴィン・ゲイのライヴを体験、アレサ・フランクリンがテレビ番組で「シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン」を歌っているのを見て大感激している(もともとアレサのColumbia時代、つまりジャズ指向の頃から彼女の歌は聴いていたらしい。その当時の作品にはあまりピンとこなかったとのことだが)。渡辺明(守安祥太郎『幻のモカンボ・セッション'54』に参加)率いる“リズム&ブルーセス”をバックにしていたこと、やはり一時期バックを務めていた“ザ・モージョ”に本田竹広が在籍していたことなどにも触れておきたいところだが、冗長に書いていく行為ほど、パンチの利いた歌にふさわしくないものもないと思うので、このあたりで切り上げる。
それにしても69年頃の雑誌報道で伝えられていた、日野皓正クインテットとの共演アルバム・レコーディングは果たして実現したのだろうか? 2枚組LP『全日本ジャズ・フェスティバル’69』、CD『内田修ジャズコレクション カタログVOL.2 Late60's』で各1曲(いずれも「いそしぎ」)聴けるのが当時の共演のすべてなのだろうか? もしこのセッション(スタジオ録音と思われる)が手つかずのまま残っているのなら、これは「ゴーカート事故直前の赤木圭一郎が西田佐知子とのデュエットで残したとされるジャズ・ソング」(ピアノの椅子に座る2ショット写真は残っている)、「ビクターに吹き込まれたらしい高柳昌行と菅野光亮のデュオ」と並ぶツチノコ級のお宝であろう。ゼヴ・フェルドマン級のジャズ探偵が生き生きと動き回れる環境が日本に生まれることを願う。


新型コロナウィルスの蔓延から、もう3年目になる。さすがに今年は外国人ミュージシャンの来日が増加傾向にあり、客席の50%がライヴ収容の上限ということもなくなってきた。マスク着用のうえ検温や消毒に協力していれば、とりあえず日々のモロモロはつつがなく過ぎるようになってはきた。コロナ禍以降、皆さんはおそらく「聞き取る力」と「読み取る力」が著しく伸びたのではなかろうか。ぼくも個人的にそれを感じている。端的にいえばマスク越しに相手がしゃべっていることを捉えるための耳の能力が増し、両目の下の、たとえば以前なら笑顔の時に見えていたであろう歯などのファクターがなくても、相手の目の細め方や大きくし方を見ることによって、その人がどの程度、嬉しがっていたり楽しんでいたりしているのかなども測れるようになってきた。こうして生き物はアップデイトされていくのだ。
コロナ蔓延元年の2020年は、本当に多くのひとたちをこの世から奪い去った。コロナが原因の方もそうでない方も、多数の方がいなくなった。今回ご紹介する弘田三枝子もこの年の7月21日に亡くなっている。60年間に及ぶ現役活動中に残した多数の作品をオリジナル盤で集めることは不可能に近いのではないか(とくに60年代のアイテムたるや、シングル盤、10インチLP、12インチLP、コンパクト盤、ソノシートが混在していて、すさまじい)。三回忌ということもあるのだろう、この2月23日には、CD6枚+DVDボックス『弘田三枝子・プレミアム』がリリースされた。ディスク1から3は「シングルズ」、ディスク4はそれ以外の洋楽カヴァー中心、ディスク5は洋楽カヴァーや日本語詞曲で構成されていて(「シェーク・アンド・ロール」のR&Bフィーリングは鳥肌もの)、ディスク6は「アスパラで生き抜こう」などのCMソングや大ヒット「人形の家」の英語ヴァージョンなども含むレアリティーズ集、そしてDVDには紅白歌合戦での歌唱などが収められている。特にジャズファンにとって嬉しいのは古典的一枚『ニューヨークのミコ ニュー・ジャズを唄う』からの曲や、菊地雅章や渋谷毅のアレンジ曲が入っていること。入手してからずっと、ぜひ取り上げたいと思っていたのだが、全138曲収録というすさまじいボリュームであるし、弘田三枝子のパンチのある歌は聴き流すには手ごたえがありすぎるので、じっくり味わっていたところ、発売からずいぶん遅い紹介執筆になってしまったのである。
弘田三枝子は中学1年生の頃から米軍キャンプで研鑽を積んだ後、60年7月にテレビ番組「ヒット・キット・ショー」のオーディションでアーヴィング・バーリン作「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」を歌って合格。61年11月に東芝音楽工業からデビュー・シングル「子供ぢゃないの」を発表した。当時の東芝には梅木マリ、ベニ・シスターズ、香山ユリ、斎藤チヤ子、富永ユキ、少しおねえさん系では朝丘雪路などガール・ポップスの宝庫という印象があるのだが、個人的には、あの、なんともいえない隙間感が愛おしい東芝モノラル・サウンドに弘田三枝子の歌声は分厚すぎるのではないかと思うこともしばしばだ。もっともモノラルなのはシングル盤だけで、10インチLP『弘田三枝子 スタンダードを唄う』(63年)あたりはステレオ盤も出ているのだが、自分にとっての彼女の醍醐味は、64年の日本コロムビア移籍以降のステレオ録音による、ごく自然な広がりのある伴奏トラックと、パンチの利きを維持しつつも押しと引きを絶妙に心得るようになった歌声の数々だ。『弘田三枝子・プレミアム』ではディスク1の13曲目「はじめての恋人」からコロムビア音源が始まる。発表は64年12月、ということは、コロムビア史観でいくと、その前月にあたる11月には美空ひばりが「柔」、さらにその前月の10月には都はるみが「アンコ椿は恋の花」を出している。つまり演歌のメガ・ヒットが出まくっていたときに、ポップス・シンガー弘田三枝子は他社からひょっこりやってきたことになる。
自宅には1000枚ものレコードがあり、雑誌のお部屋訪問的口絵にはエラ・フィッツジェラルド&ネルソン・リドル『エラ・スウィングス・ブライトリー・ウィズ・ネルソン』、ダイナ・ワシントン『アフター・アワーズ・ウィズ・ミスD』、オスカー・ブラウンJr.『ビトウィーン・ヘヴン・アンド・ヘル』、アーネスティン・アンダーソン『モーニン・モーニン・モーニン』、レイ・チャールズ『ジニアス・ヒッツ・ザ・ロード』等のジャケットが見える。その歌唱は、62年に来日したキャピトル・レコードのスタッフにも称賛されたとのことだし、64年には渡米してミュージカルを勉強したり作曲家ジミー・マクヒュー(「オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート」等を書いた)に会う予定もあったようだが、実際のところ、まだ敗戦から十数年ほどの日本では、どの程度、確かだと保証できる海外進出プランが存在したかどうかはわからない。が、アメリカで歌唱するチャンスは突如、おそらく最上といえる形でやってきた。
昨年9月に93歳で亡くなったプロモーター、ジョージ・ウィーン------「ストーリーヴィル」と名乗るジャズ・クラブやレーベルを率い、長くニューポート・ジャズ・フェスティバルのブッキングに関わり、スウィング・ジャズ系ピアニストとしても数々のアルバムを残す人物だ。映画『真夏の夜のジャズ』の舞台となった1958年度のニューポートにも当然ながら全面的に関わっていたのだが、おそらく意図的に名前のクレジットが外されるという忸怩たる思いも経験している。彼が自らブッキングに関与した「第1回世界ジャズ・フェスティバル」(第2回以降はなかった)のため、マイルス・デイヴィス・クインテットをはじめとする錚々たる音楽家たち、評論家レナード・フェザーなどと共に初めて日本の土を踏んだのは東京オリンピックの年、64年夏のこと。ウィーンは日本に大きなビジネスの可能性を感じたのだろう、65年1月、今度は「第二回ドラム合戦」というコンサートの責任者として再来日した(ドラマーはフィリー・ジョー・ジョーンズ、チャーリー・パーシップ、バディ・リッチ、ルイ・ベルソン)。どうやら、この訪日はニューポートに日本人ミュージシャンを招聘するためのスカウトを兼ねたものでもあったらしい。ウィーンはオーディション(弘田三枝子ひとりのために行なわれたのか否かは不明)で三度にわたって彼女の歌(「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」等)をテストし、「まだ英語に難はあるが、大物になる素質あり」とニューポート行きを認めた。
彼女がアメリカ本土に到着したのは6月下旬とされる。ステージは7月3日が本番だったが、少なくとも、前日の2日にはロードアイランド州ニューポートの野外特設会場に顔を出していた。というのもセロニアス・モンクに挨拶し(モンクの国内盤新譜は当時、日本コロムビアから出ていた)、ジョン・コルトレーンと記念撮影をしているからだ。コルトレーンとの写真には和服のもの(コルトレーンは弘田の肩に手をかけている)と洋装のものがある。どこかのタイミングで着替えたということなのだろうが、その間、コルトレーンがじっと待っていたのかと思うとなんだか微笑ましい。
ここで65年度ニューポートの主な出演者を、当時のパンフレットからひいておく。
7月1日(初日) メンフィス・スリム、ピート・シーガー、マディ・ウォーターズ・ブルース・バンド(ジェイムズ・コットン参加)、ディジー・ガレスピー、レス・マッキャン、ジョー・ウィリアムスなど
7月2日(昼の部) ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ、アーチー・シェップ、ポール・ブレイ、セシル・テイラー
7月2日(夜の部) アート・ブレイキー、カーメン・マクレイ、マイルス・デイヴィス、セロニアス・モンク、ジョン・コルトレーン
7月3日(昼の部) ドラム・ワークショップ:ルイ・ベルソン、アート・ブレイキー、ロイ・ヘインズ、エルヴィン・ジョーンズ、(パパ・)ジョー・ジョーンズ、ジョー・モレロ、バディ・リッチ
7月3日(夜の部) ジャム・セッション(イリノイ・ジャケー、秋吉敏子、トニー・スコット他)、弘田三枝子、デイヴ・ブルーベック、ハービー・マン、アール・ハインズ、デューク・エリントンfeatルイ・ベルソン
7月4日(昼の部) デニー・ザイトリン、ウェス・モンゴメリー+ウィントン・ケリー、アッティラ・ゾラー、ダラー・ブランド、スタン・ゲッツ
7月4日(夜の部) オスカー・ピーターソン、カウント・ベイシー+フランク・シナトラ
ヨダレがこぼれそうなほどすごいメンツだ。弘田三枝子は会場でエリントン、カーメン等のパフォーマンスを満喫したらしい。なんたるうらやましさ。もしニューポート入りが早まって7月2日昼のステージを目の当たりにしていたら、帰国後、日本初のフリージャズ歌手になるという、別の道が開けていたかもしれないとも妄想してしまう。
65年度ニューポートには、評論家の本多俊夫(サックス奏者・本多俊之の父)や、カメラマンで後年ベーシストとして認められる中村照夫なども足を運んでいたはずだが、ぼくの知る中で弘田三枝子のステージを詳細にレポートしているのは原田信夫(ムード歌謡グループ“ザ・キャラクターズ”のリーダー。原信夫とは別人)だけだ。弘田は大雨がやんでから登場し、「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」、メモを見ながらの英語のあいさつ、「ミスティ」、「ムーン・リヴァー」、「マック・ザ・ナイフ」、前田憲男アレンジの「三階節」を聴かせた。現場を捉えたカラー写真を見ると当日の弘田はピンク色のドレスを着て、すごく嬉しそうな表情をしている。一部で“スタン・ゲッツ楽団が伴奏予定”と報じられていたものの、当日のサポート陣はビリー・テイラー(ピアノ)、ベン・タッカー(ベース)、グラディ・テイト(ドラムス、現場写真ではバスドラに“BR”とのイニシャルがある。バディ・リッチの楽器を使ったのか)、ほかトニー・スコット(クラリネット)も加わったようだ。いわゆる進駐軍として日本滞在の経験があるはずのタッカー、一時期日本に住んでいたスコットの存在は弘田に大きな安心感を与えたことだろう。日系二世のパット鈴木を別にすれば、日本人のニューポート参加は秋吉敏子(56年初登場)に続いて、二人目だったのでは。67年にはビッグ・バンド“原信夫とシャープス&フラッツ”、68年には渡辺貞夫が単身で登場している。そのときサポートしたのもビリー・テイラーだった。
ニューポート出演を終えた弘田三枝子は、ニューヨークに向かう。アルバム・レコーディングのためだ。日本の流行歌手は当時、あくまでもシングル盤第一主義で、アルバムが出たとしてもそれはシングル集的なものが多かった。そんな時代に、アルバム単位の吹き込みが、しかもニューヨークで実現したのは、いくら実力のある歌手だとしても奇跡的なことではないか。銭湯入浴料28円だった頃、1ドル360円だった頃の話なのだ。

7月5日から、弘田はベン・タッカーのレッスンを受けた。「本物のジャズをつかみなさい」と、ユセフ・ラティーフのリハーサルに連れていかれたこともあるようだ。伊藤貞司(マヤ・デレンの夫で、打楽器奏者としてハービー・マンと共演。死後、ジョン・ゾーンのTzadikレーベルから作品リリース)とも知り合った。レコーディングのディレクターは、クインシー・ジョーンズお気にいりのピアニストで、ビートルズやハーブ・アルパート&ティファナ・ブラスがとりあげた「ア・テイスト・オブ・ハニー(蜜の味)」の作者であるボビー・スコットが務めた。ほか、コーディネイターとして、当時ニューヨークにいた宮田英夫も協力した。宮田ハーモニカで有名な宮田東峰の子息で、70年代に菊地雅章や日野皓正などのバンドでサックスを吹いた彼の若き日の姿である。
収録は、フィル・スペクターとレスター・シルのレーベル“フィレス”のニューヨーク録音分によく使われたミラ・サウンド・スタジオで行なわれた。ぼくは“日本コロムビアの商品なのだから、米国コロムビアが誇るマンハッタン30丁目スタジオが使われたのだろう”と勝手に思っていたのだが。『ニューヨークのミコ ニュー・ジャズを唄う』という標題はなかなか意味深で、いわゆるスタンダード・ナンバーは含まれていない。日本語一切なしの英語オンリー、曲数は全8トラックと少なめで、歌詞の出てこない(スキャットだけの)曲もある。とにもかくにも、この作品は、英語が母国語ではないものの子供の頃から英語の歌に親しんできた弘田が、限られた日数の中で精一杯取り組んだ努力の証だ。
同アルバムがいま改めて評価されているのは、おそらく世界最初に「サニー」や、ビリー・テイラー作「アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー (ハウ・イット・ウッド・フィール・トゥ・ビー・フリー)」のヴォーカル・ヴァージョンを収録したこととも関係するのだろう。その後「アイ・ウィッシュ~」はニーナ・シモン(67年)、ソロモン・バーク(68年)、マリーナ・ショウ(68年)らによって歌われ、公民権運動の代名詞的ナンバーと言えるほどの支持を集めていく(近年、アンドラ・デイも歌った)。だがそれらも弘田が録音した後の出来事だ。いっぽう、ボビー・ヘブが書き、彼自身の歌によって66年に大ヒットすることになる「サニー」は、ベン・タッカーが仕掛け人となって世に出た一曲といえる。タッカーの談話を紹介したい。
“ハービー・マンのバンドでグリニッチ・ヴィレッジの「ヴィレッジ・ゲイト」に出ているときにボビー・ヘブがやってきた。“君が作った「カミン・ホーム・ベイビー」は僕のレパートリーの一つなんだ。セカンド・アヴェニューのライヴ・スポットで歌っているから聴きにきてよ”というので、その近所に住んでいたし、ふらっと聴きに行ったら素晴らしかった。そこで私は“君の曲も聴きたいな”と言ったところ、彼は「サニー」を歌い出した。最高だった。翌日、マーキュリー・レコーズに彼を連れて行って、(当時マーキュリーの音楽監督的存在のひとりだった)ボビー・スコットに引き合わせた”。
実のところは、タッカーとヘブが出会い、マーキュリーがゴーサインを押すまでに数カ月が流れている。その間に「サニー」をレコーディングしたのは弘田三枝子だ。“彼女自身が楽曲リストの中から選んだ”という、いかにも伝説になりそうな話もあるようだが、実際はタッカーの知り合いの音楽出版社が持っている(おそらく)安くて、まだあまり注目されていない曲のリストの中から、タッカーが強く推したのではないか、というのが個人的な推測だ。
68年2月、弘田は二度目のアメリカ修行をおこない、ロサンゼルスの「ココナッツ・グローヴ」でマーヴィン・ゲイのライヴを体験、アレサ・フランクリンがテレビ番組で「シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン」を歌っているのを見て大感激している(もともとアレサのColumbia時代、つまりジャズ指向の頃から彼女の歌は聴いていたらしい。その当時の作品にはあまりピンとこなかったとのことだが)。渡辺明(守安祥太郎『幻のモカンボ・セッション'54』に参加)率いる“リズム&ブルーセス”をバックにしていたこと、やはり一時期バックを務めていた“ザ・モージョ”に本田竹広が在籍していたことなどにも触れておきたいところだが、冗長に書いていく行為ほど、パンチの利いた歌にふさわしくないものもないと思うので、このあたりで切り上げる。
それにしても69年頃の雑誌報道で伝えられていた、日野皓正クインテットとの共演アルバム・レコーディングは果たして実現したのだろうか? 2枚組LP『全日本ジャズ・フェスティバル’69』、CD『内田修ジャズコレクション カタログVOL.2 Late60's』で各1曲(いずれも「いそしぎ」)聴けるのが当時の共演のすべてなのだろうか? もしこのセッション(スタジオ録音と思われる)が手つかずのまま残っているのなら、これは「ゴーカート事故直前の赤木圭一郎が西田佐知子とのデュエットで残したとされるジャズ・ソング」(ピアノの椅子に座る2ショット写真は残っている)、「ビクターに吹き込まれたらしい高柳昌行と菅野光亮のデュオ」と並ぶツチノコ級のお宝であろう。ゼヴ・フェルドマン級のジャズ探偵が生き生きと動き回れる環境が日本に生まれることを願う。

最新ニュース
-
2024.04.09
- JAZZ
-
2023.11.21
- JAZZ
-
2023.07.20
- JAZZ
-
2023.04.25
- JAZZ
-
2022.11.24
- JAZZ
-
2022.06.14
- JAZZ
-
2022.01.19
- JAZZ
-
2021.11.25
- JAZZ
-
2021.08.31
- JAZZ