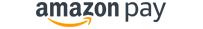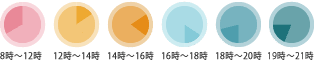- おすすめキーワード
-

<連載>原田和典のJAZZ徒然草 第128回
- JAZZ
- JAZZ徒然草
2024.05.13
ルーツと先端が混在した街、NYのヴァイブレーション。俊英ドラマー/作曲家の森智大が、最新作『Prana』と来日ツアーについて語る
“NYのジャズシーンにさらにコミットし、アルバム制作やツアーを通じて様々なアプローチでビバップを学び、これからは「NY在住のドラマー」ではなく、「NYのジャズシーンから必要とされるドラマー」になります。その上で自分のジャズを表現したいと思っています”
なんと頼もしい言葉だろう。ドラマー、森智大が5月15日にサード・アルバム『Prana』を発表する。ジャズの歴史や伝統を愛し、さまざまなリック(技と言えばいいか)を識る彼が、そのうえで放つ、今、この時のジャズ。初めて取り組んだというストリングス・アレンジも含め、実にスリリングな、聴きごたえに満ちた一作である。5月末から行われる凱旋ツアーを前に、取材に応えていただいたのでここに紹介したい。
---- 『Prana』では伝統的なバップと、コンテンポラリーなサウンドの両方が味わえます。こうした構想はどのようにして生まれたのでしょうか?
NYではビバップのようなジャズのルーツになる音楽やジャズと他ジャンルを融合させた最先端な音楽が混在しています。ビバップのシーンもまだまだ健在で、そのような土壌がしっかりあるからこそ最先端なものも生まれていると言えます。私はコロナ禍で日本へ一時帰国しており、NYとは対照的に少しのんびりしている地元福岡に2年間滞在していました。NYと日本での経験や学んだ表現を一枚のアルバムに収めました。
---- アルバム・タイトルにはエネルギーや生命力という意味があるそうですね、
エネルギッシュな人々が世界中から集まるNYに身を置いてきたからこそ培われたメンタリティでコロナ禍でも楽しく、充実した時間を過ごすことができました。コロナ禍で貯めてきたものを今こそ爆発させて、今後さらに飛躍していきたいと思ってつけました。ジャケット・デザインも、「コロナ禍を経て傷だらけになりながらも、力をつけた無双のアライグマ(Raccoon)が敵(ウイルスやウイルスによる影響)を倒し、未来を切り開いていく」というアイディアから生まれました。
---- 森さんにとって、バップ(モダン・ジャズ)の魅力とは何でしょうか?
初心者から上級者まで誰もが演奏でき、リード譜と呼ばれるメロディとコードしか書いていない1〜3ページの楽譜で1曲を演奏するようなとてもシンプルな音楽だからこその奥深さに魅力を感じています。NYではたくさんのところでビバップが演奏されています。レジェンドたちとのギグやセッションで共演する機会もたまにめぐってきて、演奏以外のミュージシャンシップも学べます。
---- モダン・ジャズ・コンボのアレンジで心がけていることは?
ジャズの演奏はシンプルな構成上、どうしても同じになりがちなので、まずは自分達が飽きないように、そしてお客さんたちに「こんなに選択肢があるのか」と思っていただけるように視野を広げて演奏することを心がけています。
---- 作曲に積極的に取り組むようになったのはいつからでしょうか?
作曲は小さい頃からしていましたが、ジャズの作曲は大学生から始めました。誰かに習ったわけではなく、とりあえず自分の耳を頼りに書いてみて、共演するプレイヤーたちからアドバイスをいただきました。
---- ストリングス(弦楽四重奏)を起用した理由は? 今回の作品については、挾間美帆さんから学んだことが大きかったとうかがっていますが、森さんの視野はどのように変わりましたか?
ストリングスを起用した理由は、企画面で違うことをしたいと思ったからです。2022年に行ったNYのバンドでの日本ツアーではすでにアルバムの曲を演奏していたので、次のツアーで同じようことをやってもつまらないなと思いました。また、コロナ禍での補助金事業で行った、ラージアンサンブル、アルゼンチンタンゴ(バンドネオン、バイオリンなどの普段ジャズでは使われない楽器)とジャズのコラボ企画を通じて、様々な編成での演奏に魅力を感じ、次のアルバム、そしてツアーに必要なピースはストリングスを加えることだと思いました。
挾間さんのレッスンを通して、理論的に正しいか正しくないかだけでなく、自分の耳で聴いてこの響きが好きかどうか、何か意図があってこのアレンジにしたのかなど、自分の曲と根本的に向き合いながら、突き詰めて考えさせられることが本当に多かったです。また、プレイヤーが音楽や楽器の歴史、先人たちの演奏について学んで、自分の演奏スタイルを確立するのと同じように、作編曲も先人たちの作品を聴き、分析し、それを踏まえて自分の作品づくりに落とし込む重要性も挾間さんから教えていただきました。
---- 四重奏の人選は?
弦楽器奏者の知り合いがほとんどいなかったため、ストリングスとのプロジェクトをしているピアニスト・作編曲家の江﨑文武さんにチェリストの村岡苑子さんを紹介していただきました。村岡さんは江﨑さんのプロジェクト、King Gnuなどのアーティストのサポートをされており、様々なスタイルの音楽に対応できるということでお願いしました。カルテットは村岡さんが普段から一緒に演奏しているチームです。
---- ジャズ・コンボの皆さんについて、コメントをいただけますか?
トランペットのベニー・ベナックは日本や世界でも大人気で、トランペットの他にピアノやボーカルもこなし、多くのファンを魅了する生粋のエンターテイナーです。彼はいつも音楽の純粋な楽しさや魅力を教えてくれます。アルトサックスの寺久保エレナは私と同い年、そしてバークリー音楽大学の同期で、10代の頃から天才として世間から注目されてきました。その中で彼女がNYで真摯に音楽と向き合い、貪欲に活動している姿にいつも刺激を受けています。ピアノの山中みきさんも10年来の友人で、お互い渡米したての頃からの付き合いです。いつもパワーあふれるみきさんの人柄や演奏に元気付けられるとともに、ジャズの新たな可能性に気付かせてくれます。ベースのラッセル・ホールは10代の頃からNYのジャズシーンで活躍しており、私は学生の頃から彼といつか一緒に演奏するんだと心に決めていました。協調性のある演奏だけでなく、時には型にはまらず常識を壊すような斬新な演奏が彼の持ち味です。小川慶太さんに関しては、同じ九州出身ということで学生時代から存在は知っていました。慶太さんはドラム、パーカッションあらゆる楽器を使いこなし、ジャンル問わず、たくさんの引き出しを持っていて、どんな曲にも対応されます。また、慶太さんはプレイヤーとして何より大事な「グルーヴさせる能力」が飛び抜けており、制作を通じて「グルーヴ」について考えさせられました。
レコーディング中のひとこま。左から山中みき、ベニー・ベナック、森智大、ラッセル・ホール、寺久保エレナ
---- ラスト・ナンバー「Heights [Bonus Track]」にドラムが入っていないのも印象的でした。
今回のアルバムでは、素晴らしいストリングスのメンバーに参加していただいたので、その4人をフィーチャーし、自分は演奏せずにストリングスカルテットのみで収録しました。すでに世に出している楽曲ということもあり、CD盤のみのボーナストラックとなっています。
---- コロナ前とコロナ後、音楽的に最も大きく変化したことは?
2022年のNYのメンバーとのツアーをきっかけにジャズのレコードをさらに聴くようになり、「ジャズを演奏する」ということの解像度が上がったかもしれません。歴史とNYの今を体現できるようにこれからも精進します。
---- ところで、初めて意識した音楽は何ですか?
Beatlesです。小さい頃はBeatlesの曲をドラムで叩いていました。
---- 3歳からドラムを始めたとのことですが、ペダルに足は届きましたか?
最初から大人のドラムセットを用意してもらったのですが、足は届かなかったので手だけで叩いていました。家族でバンドもしていましたし、たまに両親のバンドに入れてもらって叩いていました。
---- ジャズを好きになったきっかけは何ですか?
中学生の時に習っていたドラムの先生がジャズをメインに演奏されているドラマーだったこと、同じピアノ教室の江﨑さんがジャズに興味を持ち、一緒にバンドをやることになったことがきっかけです。よくあるような「この曲を聴いて衝撃を受けて・・・」というのはなく、たまたま流れでジャズをよく演奏するようになりました。
---- バークリーでRalph Peterson Jr, Terri Lyne Carrington、ニューヨークではKenny Washington等に師事なさいましたが、彼らから何を学びましたか?
渡米当初は何か魔法のような指導があるのではないだろうかと様々なドラマーのレッスンを取りましたが、結局は基礎基本の重要さやどれだけシンプルにグルーブさせられるかということを一番学びました。先生によってそれぞれアプローチは違いましたが、特別な指導法はなく、誰にでも理解できるシンプルなことを繰り返し実行し、コツコツ積み重ねていくということが根本にあるということを気付かされました。
---- ニューヨークに渡った動機は何ですか? その魅力は?
世界中からミュージシャンたちが集まり、しのぎを削っている環境に身を置き、自分の表現を追求したかったからです。また、NYと日本をつなぎ、日本でもNYのジャズを気軽に聴けるような機会を作る存在になりたいと思ったからです。ミュージシャンたちの演奏レベルが高いのはもちろんですが、NYという街が音楽性、メンタリティ、コミュニケーションなど様々なことを教えてくれます。そのような環境にしばらくは身を置きたいと思っていたのでコロナ後も迷わずNYへ戻りました。
---- ジャンルを問わず、好きなミュージシャンを、いくつか教えていただけますか?
ロック:Beatles, Queen, Deep Purple, Police
R&B: Tower of Power, Earth, Wind & Fire, Hiatus Kaiyote
ジャズ(ビバップ以外): Tigran Hamasyan, Brad Mehldau
クラシック:Bartok
---- 日本のファンにメッセージをお願いします。
今回のアルバム、そしてリリースツアーではいろんな楽器や編成を楽しめますし、ジャズの本質を押さえながらも、エンターテイメント性溢れるものになると思います。普段からジャズを聴かれている方もそうでない方でも、ジャズの新しい魅力を感じていただけるはずです。このメンバーでどこまでみなさんをびっくりさせられるか、とてもワクワクしています。「表現」というと演奏や制作が表に出がちですが、企画を考え、実行、運営することも「表現」の一つだと私は思っています。すべての「表現」をみなさんに存分に楽しんでいただけたら嬉しいです。各会場でみなさんにお会いできるのを楽しみにしています。
■森智大『Prana』リリースツアー
5/30(木)& 31(金) 札幌D-Bop(クインテット編成)
6/1 (土)岡山SOHO(クインテット編成)
6/2 (日)福岡Rooms (with Strings)
6/3 (月)神戸100BAN Hall(クインテット編成)
6/4 (火)東京WWW (with Strings)
森智大ホームページ: https://tomohiromori.com/
-
NYを中心に世界で活躍するジャズミュージシャンたちが集結!
2024年05月31日 / CD / JPN
最新ニュース
-
2024.04.09
- JAZZ
-
2023.11.21
- JAZZ
-
2023.07.20
- JAZZ
-
2023.04.25
- JAZZ
-
2022.11.24
- JAZZ
-
2022.06.14
- JAZZ
-
2022.05.11
- JAZZ
-
2022.01.19
- JAZZ
-
2021.11.25
- JAZZ