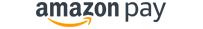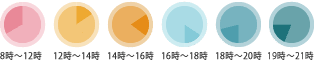- おすすめキーワード
-

<連載>原田和典のJAZZ徒然草 第100回
- JAZZ
- JAZZ徒然草
2017.02.21
ねこ、猫、ネコ、NEKO、(=^・^=)!!! 今年は「ねこの日」30周年。チェロ奏者デヴィッド・タイと、トランペット奏者ジョー・ニューマンの新旧“ねこCD”を聴きながら、マッタリしたひとときを過ごそうぜ
2月22日は「ねこの日」であるという。
何をいうか、俺は私は1日24時間1年365日ねこのことを考えているよ、エヴリデイ・イズ・ア・キャット・デイだよという猫好きの方も数多くいらっしゃるのではないかと思う。「ねこの日」が制定されたのは1987年。つまり今年でちょうど30周年を迎える。これは日本独自の制定であり、動物愛護団体・国際動物福祉基金が決めたInternational Cat Dayは8月8日だ。
自分が「ねこの日」を知ったのは今から6~7年前、遠藤ミチロウさんにインタビューした時のことだ。ミチロウさんのライヴは何度もいろんな組み合わせで見ているが、いつだったかの8月6日、ぼくは広島市で「爆心地ライヴ」というタイトルの、燃えるようなパフォーマンスを体験した。「音泉ファック」、「オデッセイ・20××・SEX」、「お母さんいい加減あなたの顔は忘れてしまいました」、ボブ・ディランの曲に感動的な日本語詞をつけた「天国の扉」などなど、矢継ぎ早の名曲群に、すっかり心をわしづかみにされた。途中、休憩があり、ミチロウさんはどこかにはけ、ぼくも真夏の満員の室内に息苦しさを覚えていったん外に出て駐車場のほうに歩いていったのだが・・・そこで見たのは背中を丸くして野良猫をナデナデしているミチロウさんであった。そうなると、こちらも「ねこ、好きなんですか?」と問いかけずにはいられない。「大好きで、家でも飼ってるんですよ。だけどツアーが始まるとなかなか会えなくてね」「そうですかー」と、ほんのちょっと雑談させてもらった。この段落の最初に触れたインタビューは、それから数年後の出来事である。イアン・アンダーソン(ジェスロ・タル)やハービー・マンのフルートに憧れたとかラリー・コリエルのギターが衝撃的だったとかドン・チェリーも好きですよとかビル・ラズウェルやソニー・シャーロックとセッションをおこなったときの逸話など、いろいろ興味深いお話をうかがった最後に、「そういえば今日は2月22日、ねこの日なんですよ」と突如、話を振ってきてくれたのはなんだかとてもうれしかった。
そして2017年の“ねこの日”、実に興味深い一作が登場する。アメリカ人チェロ奏者/作曲家、デヴィッド・タイの『ねこのための音楽– Music For Cats』というアルバムだ。
いちおうジャンルとしては“クラシック”ということになるのかもしれないが、ぼくは現代創作室内楽として楽しんだ。1956年生まれの彼は、アゼルバイジャン出身の名匠ムスティスラフ・ロストロポーヴィチに認められ、84年ワシントン・ナショナル交響楽団に入団。サンフランシスコ交響楽団でも首席チェリストを務め、2013年から2016年にかけてはエクリプス室内管弦楽団で音楽監督を担当していたという。ジャズ界との交流はとくに伝えられていないものの、ヘヴィーメタルとクラシックの融合として話題を集めたメタリカの『S&M』にも参加、やはりメタリカがらみのプロジェクトである“エコーブレイン”の同名アルバムのストリングス・アレンジも担当。5度のグラミー受賞歴を持つ大御所カントリー・シンガー、メアリー・チェイピン・カーペンターの『A Place In The World』にも名前がクレジットされている。
醸造場でクラシックをかけると酒の味がまろやかになるとか、ラウド・ロックをかけると植物が枯れるとか、まあ、そのたぐいの話を目にしたり耳にしたりすることはある。誰かの歌にあわせて合いの手を入れる犬や、人間の歌声そっくりに反芻する鳥などの映像をごらんになった方も少なくなかろう。ただこれは、「人間の音楽家が人間のリスナーが聴く目的で作った音楽に、動植物はどう反応するか?」ということに対する反応であり結果だ。マイケル・ジャクソンもビートルズも、当たり前だが「人間が、人間に向けて作った音楽」である。しかしデヴィッドはそれをさらに一歩前進させ、「まずなによりも動物に聴いてもらうこと」を目的に、さまざまな研究や調査を重ねてコンポジションにとりかかった。最初に楽曲を寄せた動物は、タマリンであるという。当コーナーでもニューヨークのセントラル・パークにいるタマリン(ウキちゃん)をしばしば紹介してきたが、あの動きのおそろしく早いタマリンこそが、デヴィッドの動物用楽曲の第一歩であったことは瞠目されてよい。
さらに2015年ころから猫に向けた楽曲制作に取り組むことを決意、その第一歩として「Applied Animal Behavior Science」という雑誌に、ねこのための音楽に関する論文を寄稿した。これが評判を呼び、クラウドファンディングでCDの制作資金を募ったところ予想を上回る応募が集まり、自主製作で1万枚以上をプレスしたところ、それがユニバーサルミュージックの目にとまり、今回の世界メジャー・リリースにつながったときく。ちなみに大手レコード会社が「人間ではないリスナーを対象にした音楽」を発売するのは、これが史上初であるらしい。
「ねこ音楽」について実際のねこがどんな反応を示したかについては、すでにテレビのワイドショー等で報じられている通り。ゴロゴロと喉を鳴らすときの音に似た響き(英語では“purr”という)が、静謐なロング・トーンに重なっては消える。人類はまだ猫語を解読するすべを知らないので猫へのインタビューが成立しないのが残念だが、人間である自分が聴いても、心の凝りがそっとほぐされていくような気持ちにはなった。メロディ、ハーモニー、リズムの特にどれを聴かせるというわけでもなく、チェロの妙技がフィーチャーされているわけでもないが、ECMレーベルで30数年続くニュー・シリーズや、近ごろ話題のコンテンポラリー・チェンバー・ミュージック(当コーナーでも、パトリック・ジマーリなどいくつかとりあげた)に関心のある方なら、試してみる価値はある。そしてぼくはデヴィッドに、ジャズや即興のシーンにもぜひ入り込んできてほしいと考えた。はっきりいってチェロはジャズ界における花形楽器ではないが、いま生きているひとに限定してもアブドゥル・ワドゥド(1947年生まれ、ラヒーム・デヴォーンの父)、ディードリー・マレイ(51年生まれ)、ハンク・ロバーツ(54年生まれ)、エリック・フリードランダー(60年生まれ)、坂本弘道(62年生まれ)、トメカ・リード(77年生まれ)、吉川よしひろ、橋本歩などの才人がいる。ぜひそこに入り込んで、シーンをひっかきまわし、人間も動物も植物も一体となった音世界で全宇宙を幸せのヴァイブで満たしてほしいものだ。
ねこと言えば、より伝統的なジャズのところでジョー・ニューマンの『The Happy Cats』がめでたく復刻された。
ニューマンは1922年生まれのトランペット奏者。最も高名なのは1950年代のカウント・ベイシー・オーケストラにおける活躍だろう。『エイプリル・イン・パリ』、『ベイシー・イン・ロンドン』、『アトミック・ベイシー』、あのあたりには全部入っている。60年代以降は教育活動にも力を入れ、91年に卒中で倒れるまで現役活動を続けた(92年死去)。リーダー・アルバムの数も多く、とくに50年代半ばから後半にかけては年3~4枚の割合でリリースしている。もっともこの時期はジャズ・アルバムの量産時代であるからリー・モーガンやドナルド・バードやアート・ファーマーなど当時の若手気鋭もけっこうな数を出しているのだが、ニューマンはブルーノートやプレスティッジのような(当時の)ジャズ専門の弱小会社ではなく、RCAビクターやルーレットといった大手ポピュラー・レーベルからリリースしているのだから格が違う。当然一枚あたりのプレス数も多かったことだろうし、アメリカの広い範囲にディストリビューションされていたと想像できる。しかし現時点でCDとして手に入る50年代のニューマン作品は決して多くない。「50年代=ハード・バップとファンキー・ジャズの時代」という(おそらく70年代以降に生まれた)観点で見れば、ハード・バップ志向のマイナー・レーベルとは縁のなかった彼の作品がとりこぼれてしまっても不思議ではないのだが、一度でも当時のニューマンの作品を聴いたリスナーであれば誰もが、彼の作風がいかにファンキーで、粘っこくて、味が濃く、ブルース・フィーリングに溢れているか知っているはずである。
なかでも『The Happy Cats』は、ズート・シムズとの『Locking Horns』やスウェーデンで録音された『Counting Five in Sweden』と並ぶかそれ以上の悦楽盤だ。共演者はフランク・ウェス(テナー・サックス、フルート)、エディ・ジョーンズ(ベース)などベイシー楽団の仲間に加え、イリノイ・ジャケ―やレオ・パーカーのバンドで働いたジョニー・エイシア(ピアノ)、モダン・ジャズ・カルテット加入から約1年半を経たコニー・ケイ(ドラムス)などなど。一部で“MJQのジョン・ルイスおかかえの音響効果係”ともいわれるコニーだが、彼はもともとR&B畑の、創設初期のアトランティック・レコードのセッションマンでもあった(ジョー・ターナー、ルース・ブラウン、レイ・チャールズのサポートなど)。本作ではMJQ対応フォームではなく、かつてのR&B時代を思い起こさせる熱血ドラムを披露する。さらにアレンジャーにはアル・コーン、ベイシー人脈からアーニー・ウィルキンスとクインシー・ジョーンズを抜擢。クインシーが編曲したひとつが、天才ピアノ奏者バド・パウエル作「バターカップ」であるのも非常に興味深い。バターカップの本名はアルテヴィア・エドワーズ。1953年にジャズ・クラブ「バードランド」のスタッフが身元引受人となって社会復帰を果たしたパウエルに、同クラブがあてがった二人目の女性である。一人目のオードリー・ヒルとは入籍したが短期間で離婚(パウエル側から見れば、「気づいたら、出会ったこともない女性と、いきなり入籍させられていた」ということになる)、しかしバターカップとの関係は形式上はパウエルが亡くなった66年まで続いている(もっとも、健康を崩していたパウエルを献身的にサポートしたのはフランシス・ポードラスであり、往年のガールフレンドであったメイ・フランシスであり、彼女との間に生まれたシリアであった)。また58年吹き込みのブルーノート盤『ザ・シーン・チェンジズ』に登場する少年はパウエルの実子ではなくバターカップの連れ子である。66年夏、パウエルが余命いくばくもない状態であることを何らかのルートで知ったバターカップは、親せきや友人が拒むのを押し切ってパウエルの病室に取材陣を引き連れて入り、カメラの前で、これみよがしに彼のやせ細った手を取って涙を流し、ゴスペルを歌ったという。一説には「彼女もピアニストだった」、「(パウエルが59~64年に住んでいた)パリでソウル・フード・レストランを開いていた」とも伝えられる。ポードラスの著書『Dance Of The Infidels: A Portrait Of Bud Powell』には、天才パウエルをとりまく非ミュージシャンの多くがいかに利己的で偽善だらけだったかが容赦なく書かれている。そしてオーネット・コールマンの敬意ある振る舞いがいかに晩年のパウエルの心の支えになっていたかも記されている。オーネットがセシル・テイラーと共にパウエルに会いに行く場面の描写など、ひたすら鳥肌が立った。
ねこの話題がいつしか鳥肌の話になってしまったので、今回はこれで筆をおく。次回をお楽しみに。
最新ニュース
-
2024.05.13
- JAZZ
-
2024.04.09
- JAZZ
-
2023.11.21
- JAZZ
-
2023.07.20
- JAZZ
-
2023.04.25
- JAZZ
-
2022.11.24
- JAZZ
-
2022.06.14
- JAZZ
-
2022.05.11
- JAZZ
-
2022.01.19
- JAZZ
-
2021.11.25
- JAZZ